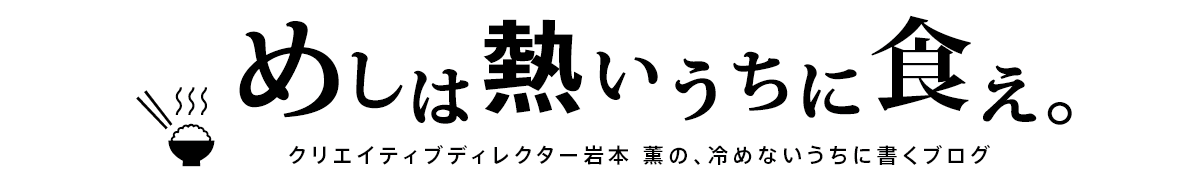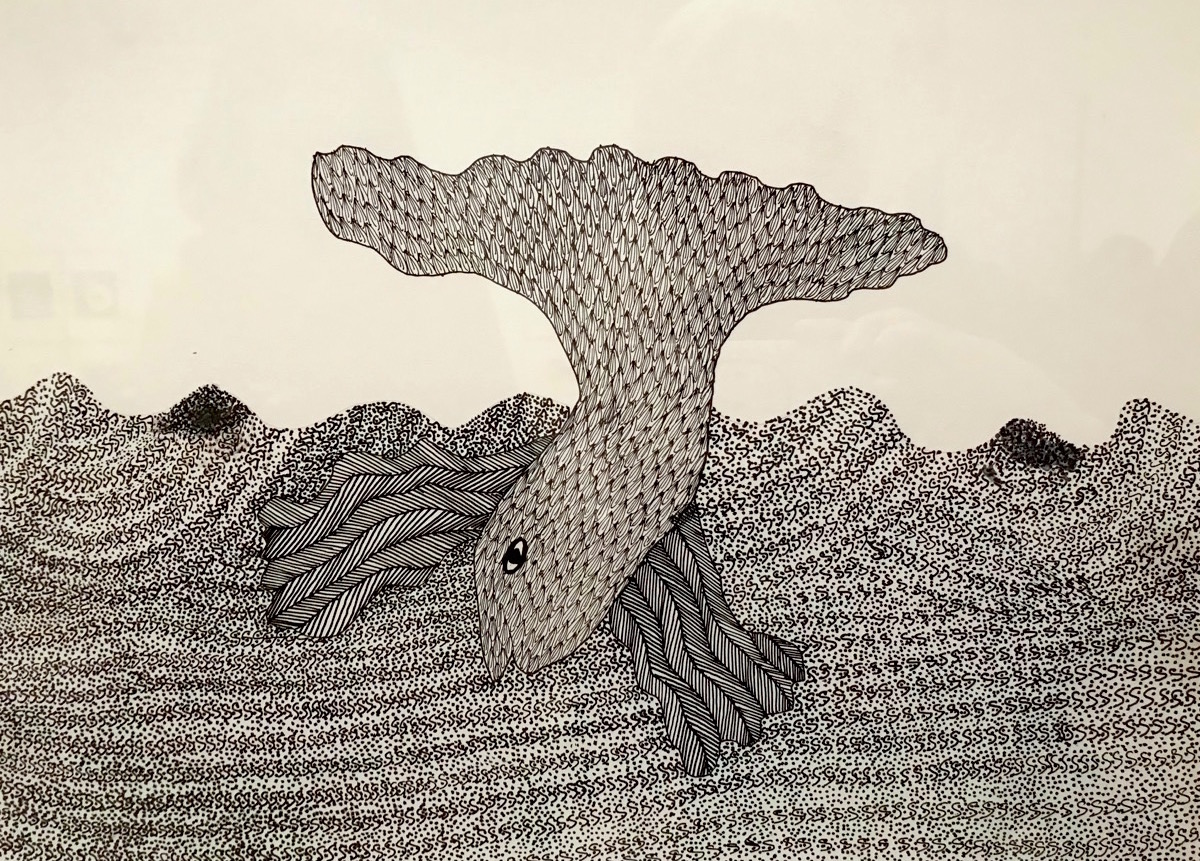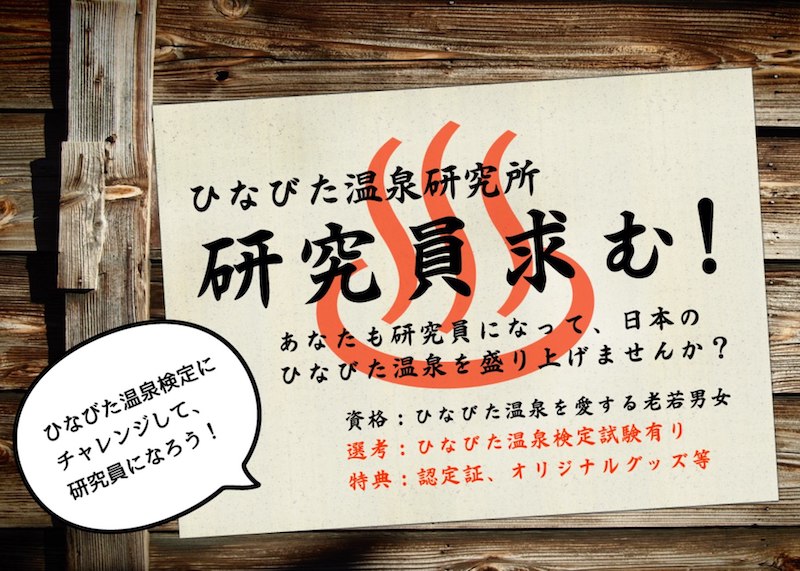藤田嗣治の、乳白色に命を吹き込む墨の線。

20世紀前半のエコール・ド・パリの日本人画家は500人以上もいたといわれる。でも、成功した画家は藤田嗣治たったひとりしかいなかった。あの佐伯祐三でさえもパリでは模倣の画家とされていた。なぜ藤田だけが成功できたのかというと、誰も見たことのない自分だけの表現を生み出すことができたから。でも、模倣もしなかったわけではない。パリに来て藤田がすぐに訪ねたのがピカソのアトリエだった。そこでキュビスムと出会って衝撃を受けた藤田は、キュビスムの習作のような絵を描いている。それは模倣というよりは、あまりにこれまでの概念を覆したその技法を、自分の身体で感じてみたかったからだろう。
キュビズムと出会ったその晩、藤田は恩師の黒田清輝からもらった絵の具箱を床に叩きつけたという。なんせ3歳の頃から画家になることを志した藤田である。日本にいたばかりに、知らぬ間に世界にものすごい遅れをとっていたことを図らずも知って、やり場のない思いが爆発したに違いない。藤田が乳白色の裸婦の絵でパリを熱狂させる8年前のことだ。
The “Milky White Nudes” 。藤田を一躍パリの寵児にした“乳白色の裸婦”が初めて世に登場したのが1921年、パリの第14回サロン・ドートンヌだった。「横たわる裸婦と猫」。透明感をたずさえた乳白色の肌。それを際立たせる深い黒。そしてその肌の輪郭として描かれた、西洋人が見たことのない魔法のように美しい墨の線……。

藤田はエコール・ド・パリの日本人画家で唯一成功した画家だったけれど、同時にまたサルバドール・ダリやアンディ・ウォーホルに先駆けて自分をアイコン化した芸術家でもあった。おかっぱ頭にちょび髭にロイド眼鏡。なぜそんな風貌にしたのか?その理由がなかなか人を食っていておもしろい。当時の世界の人気者といえば、サイレント映画のチャーリー・チャップリンとハロルド・ロイドだった。その人気者のチャップリンからはちょび髭を。ロイドからはロイド眼鏡を。おかっぱ頭は東洋人の黒髪をもっとも目立たせる髪型だから。要は世界の人気者の特徴と東洋人の髪の毛の色をいかした風貌が、おかっぱ頭にちょび髭にロイド眼鏡だったのである。藤田いわく「これで成功しないはずがないと思ったが、果たして成功したというのである」。負けず嫌いで偏屈と自認していた藤田は世界で勝負するための戦略もしたたかに考えていたのだ。
そのアイコン化した自分を描いた傑作がを、絶頂期の藤田ならではの繊細で美しい色彩で描いた1929年の自画像だろう。おもしろいのはその絵の中の藤田が絵筆ではなく面相筆を持っているところである。その筆の下には墨と硯も描かれてある。この絵はある意味、藤田が自分の成功の秘密を誇るように描いているともいえるのだ。
藤田の到達点といえる“乳白色の裸婦”は日本の浮世絵の晴信や歌麿の肌の表現から着想を得たことは有名な話。下地の紙の白さをそのまま肌の表現にする浮世絵の技法を参考にして藤田はカンバス全体に白を塗って、それに輪郭線を描き、繊細な陰影をつけて女性の肌の表現とした。そのカンバスの布も通常のものではなくシーツなどに使われる目の細かい布を張ったオリジナルのカンバスを使い、白い下地の色もシッカロールを混ぜ込むなどをして、あのパリを熱狂させた透明感あふれる乳白色を生み出したのである。そしてさらにその乳白色に命を吹き込んだのが面相筆で描かれた墨の線だった。
面相筆とは日本画の眉や鼻の輪郭など細部の線を描く細い筆のことで、藤田はその筆と墨で裸婦の輪郭を描いたのである。そんな藤田は輪郭線についてこんな事をいっている。
「線とはたんに外廓をいうのではなく、物体の核心から探求されるべきものである。美術家は物体を深く凝視し、的確の線を捉えなければならない。そのことがわかるようになるには美の真髄を極めるだけの鍛錬を必要とする」
つまり、藤田が裸体の美の真髄を捉えるために選んだのが面相筆による繊細な線(しかも墨の線)だったというわけだ。実際、藤田が乳白色の裸体の上に描いたのびやかな墨の線は息を呑むほどに美しい。そしてその輪郭線の外側が薄い白いベールのようになっているのも見逃せない。このかすかなベールがよりその繊細な線を浮き上がらせて不思議な視覚効果を生み出しているのだ。よく絵は本物を見ないとわからないなんていわれるけれども、藤田の絵はまさにそれで、この美しさはどんな高精細印刷も映像も再現できないだろう。マチエールの美を極めた藤田の絵の美しさはマチエールを通してでしか伝わらないのだ。
つまり、藤田の1929年の自画像はその乳白色に命を吹き込んだ面相筆を、さり気なく墨と硯も描き込んで、いかにも意味ありげに描いている。西洋画では馴染みのない墨と筆。それをおかっぱ頭にちょび髭ロイド眼鏡というアイコン化された藤田がもってこちらを見ている。この絵にどことなくクールなものを感じてしまうのは、藤田がアイコン化というある意味虚構の世界を生きていることを自己演出としておもしろがって描いているからではないだろうか。西洋画では馴染みのない画材を操って見たことのない美を生み出したミステリアスなアイコン化された東洋人。そんなふうに自己演出を他人を見るように描いたその距離感がこの絵には現れているように思えて、それは実に自己演出に長けた藤田らしいのだ。

現在、東京都美術館で開催中の「没後50年 藤田嗣治展」は100点以上もの藤田作品が一堂に会する、これまでで最大の大回顧展である。「風景画」「肖像画」「裸婦」「戦争画」「宗教画」などのテーマに分かれて展示され、藤田の代名詞の“乳白色の裸婦”も10点以上も展示されている。まあ、藤田ファンならば絶対に見逃せない展示会というべきものなのである。
“乳白色の裸婦”はもちろん必見で、なかでも「タピスリーの裸婦」はたまらなく美しかった。いや、思わずボクも「タピスリーの裸婦」の前で立ち尽くしてしまいました。この絵は乳白色だけではなく、そのバックのタピスリーに描かれた草花の線がまた実に美しい。そのタピスリーの美しさと、裸婦の乳白色の美しさが大きなシナジー効果を生み出していて、いよいよ美しく輝き出す。そんな絵でした、「タピスリーの裸婦」は。いやぁ、これは確かに一世を風靡する絵だなぁということが実感できた。

そしてもうひとつ、大きな見どころが藤田のニューヨーク時代の代表作「カフェ」がパリのポンピドゥー・センターから来ているところ。この絵が描かれたのが1949年。戦後30年たった藤田63歳のときの作品だ。
パリで唯一エコール・ド・パリの日本画家として成功をおさめた藤田の運命を大きく変えたのは戦争だった。太平洋戦争で戦争画を描いた藤田は敗戦後、戦争協力者として批判を浴びたのだ。それに嫌気がさした藤田は再びパリを目指そうとするが、なかなか入国の許可が下りず、GHQのツテに頼ってニューヨークへと渡った。(それだけ、とにかく日本を離れたかったのだろう。それ以来、藤田は祖国日本の土を踏むことは二度となかった)
しかしアメリカで待っていたのは日系人画家たちの冷たい態度だった。戦争協力者というレッテルがどこまでもついてきたのである。アメリカの日系人にしてみれば戦時中は収容所などに入れられて酷い扱いを受けたわけで、そうした者たちからしてみたら、戦争協力者の藤田は許しがたい存在だったのだ。
この「カフェ」は渡米したその年に描かれたもので、裸婦ではないものの、絶頂期のパリ時代の“乳白色”が久しぶりに描かれた絵でもあった。そう、藤田は絶頂期のパリ時代を終えてから“乳白色”に代わる技法を模索していて、“乳白色”を封印していたのである。なぜそれがここで久しぶりに描かれたのかはわからない。でも、この絵のモチーフがニューヨークではなく、パリであること。しかもその当時のパリではなく、かつて藤田が一世を風靡したころの古きよきパリであることを思えば、この描かれた女性の“心ここにあらず”のような表情も、そのころの自分の居場所を失った藤田の心情と無関係だとはどうしても思えない。ボクは「タピスリーの裸婦」とは別の意味でこの絵の前でまた立ち尽くしてしまった。
しかし、美しかったのは“乳白色”はもちろんのこと、女性の“乳白色”の肌を包んでいる服の黒がなんとも美しかった。藤田が描く黒は本当に美しい。それはパリ時代から変わらない。かつて藤田が東京美術学校(現在の東京藝術大学)で黒田清輝に師事して絵を学んでいたとき、卒業制作の自画像を「悪い絵の見本」と酷評され「黒を使うな」と叱られたことに反発し続けたというわけではないだろうけれど、耳を貸さなかったのは確かだろう。藤田がパリで8年間かかって生み出した“乳白色”と同時に生まれたのがこの美しい黒ではなかったか。“乳白色”をひときわ美しくする深い黒。輪郭線の墨の黒にこだわった藤田は黒の画家でもあったのだ。