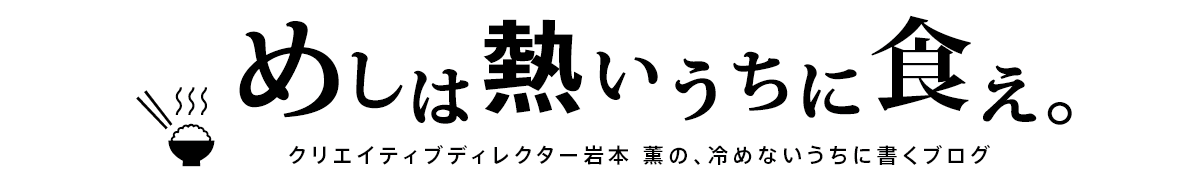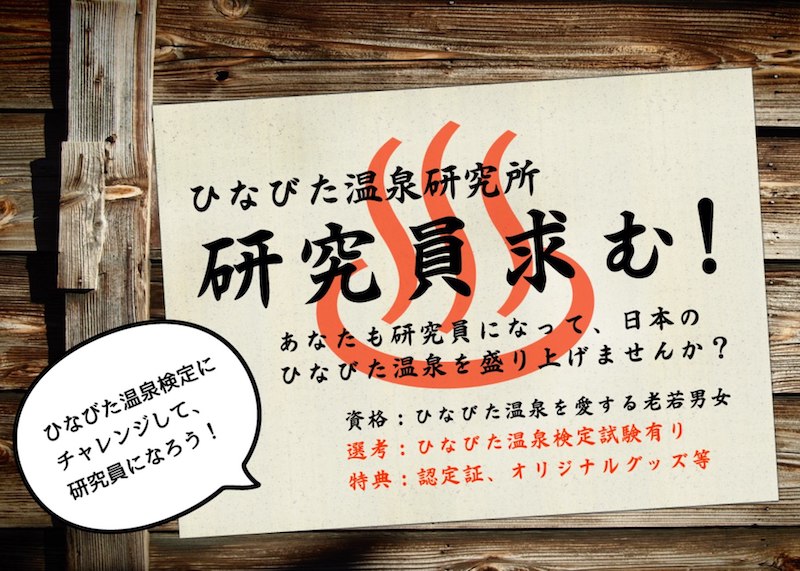生け花の小宇宙の中に立て。

生け花とフラワーアレンジメントとの違いはなにか?その答えは、かつてノーベル文学賞の記念講演「美しい日本の私」で、川端康成も引用した池坊専応の口伝の言葉の中にある。
「ただ小水尺樹をもって、江山数程のおもむきをあらわし、暫時傾刻のあいだに、千変万化の佳興をもよほす」
つまり、ほんの少しの水と花で、雄大な景勝のような、千変万化の景色を感じさせる。と、そんなことをいっているわけで、生け花とは、フラワーアレンジメントのように、花を、たんにきれいなものをつくるための素材として扱っているのではなく、花でもって世界を表現している小宇宙なのである。
生け花の起源は仏教の供花にあるとされ、日本では奈良時代から花を供えるようになった。しかし、それが生け花になるまでは長い年月を要した。和歌などで花鳥風月に親しんできた日本人は、花の美しさに対して、とりわけ繊細な感覚をもっていたが、あくまでも自然の草花を愛でるにとどまっていた。また、中国から花瓶が輸入されてきてはいたが、それは、どちらかというと花瓶自体が物珍しい工芸美術品として珍重され、花瓶のみで飾られるほうが多く、そこに花が飾られることがあっても、無造作に飾られるだけだった。
花が芸術の一形式になったのは、やはり、他の多くの日本文化と同じように足利義満の北山文化から義政の東山文化にかけての時代だった。それは立花(りっか)という様式で、なかでも池坊専慶は伝説的な名手とされている。専慶は京都の六角堂・頂法寺の僧侶だ。それまでの宗教的な供花を、彼が人の眼を楽しませるものへと変えたのが立花のはじまりだった。法要で専慶が花を立てるたびに、それを見ようと人々が押しかけたと伝えられている。そんな立花を義政の東山山荘に出入りしている同朋衆たちが、旺盛な美的探求者である義政のために取り入れたことで広まっていったのである。
花を飾って、それを目で楽しむという習慣は世界中にあるけれど、生け花のように芸術にまで高められた例は、世界広しといえども他にない。それは同時期に生まれた茶の湯もまたしかりなわけで、茶は世界中で飲まれている飲料であっても、飲料の領域を超えることはなかった。なぜ、花にせよ、茶の湯にせよ、そんなふうに日本では本来の領域を越えて高められたのか?茶の湯の場合は禅僧であった村田珠光が創始者であったことから、禅の影響がかなり色濃かった。生け花もまた、六角堂・頂法寺の僧侶であった池坊専慶がはじめたわけだったから、仏教的な思想が反映されていたのだろう。でも、いずれにせよ、それだけではなく、根底にはもっと日本人的な“なにか”があったのではないだろうか。
それは「生け花」というその呼び方自体がすでに物語っている。「生け花」とは花を「生かす」ことなのである。だから花をさす花器も華道では「花生け」という。自然に咲いている花ももちろん生きているわけだけど、その花を素材にして、そこに“命”を与えることが「生け花」なのだ。“命”を与えるということが、すなわち小宇宙の中心になるということ。ただきれいなだけではなく、絶妙なバランスと絶妙な緊張感をもって小宇宙をつくっている。利休が秀吉をギャフンといわせた朝顔の一輪挿しのあの有名なエピソードのように、ちゃんと“小宇宙として生かされた花”は、一輪の花であっても百輪の花を凌ぐ。小宇宙とはそういうことだ。小宇宙をつくる。これこそ日本文化のお家芸ともいえる“見立ての文化の系譜”だろう。
日本の生け花の歴史は池坊からはじまった。その池坊に伝わる椿の一輪挿しがある。椿の一輪挿しといえば、余計なものに削ぎ落とされた一輪挿し小宇宙の代表格だ。その椿の一輪挿しが池坊では、花びらを落としてさらに削ぎ落とされていく。江戸後期の池坊専定の時代になると椿の花びらは削ぎ落とされて6枚半になった。さらにその後を継いだ池坊専明の時代になると、なんと3枚半になった。これはもう究極の小宇宙というべきだろう。
さて、そんな生け花は、ただ漠然と「きれいだなぁ」と観ているだけではもったいない。なんせ小宇宙なのだ。じゃあ、その鑑賞方法はというと、生け花は床の間で発展してきた。だからそれには必ず“正面”がある。花器からまっすぐと花が立つ部分を「水際」といい、この「水際」が少し抜けて見える目の高さで、真正面から鑑賞する。小宇宙を形成している絶妙なバランスも緊張感も、ここから観ることでいちばん感じられる。それを感じるそのとき、あなたはその生け花の小宇宙に包まれるのである。
※当サイトのすべての文、画像、データの無断転載を堅くお断りします。