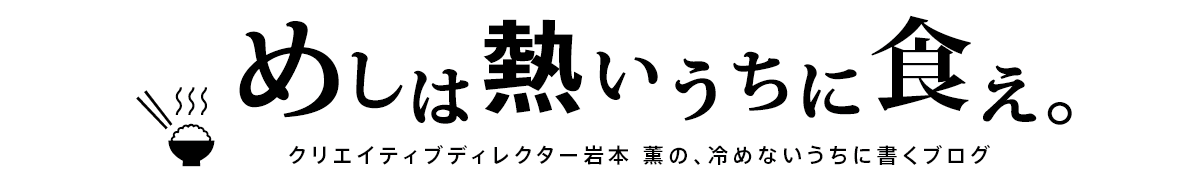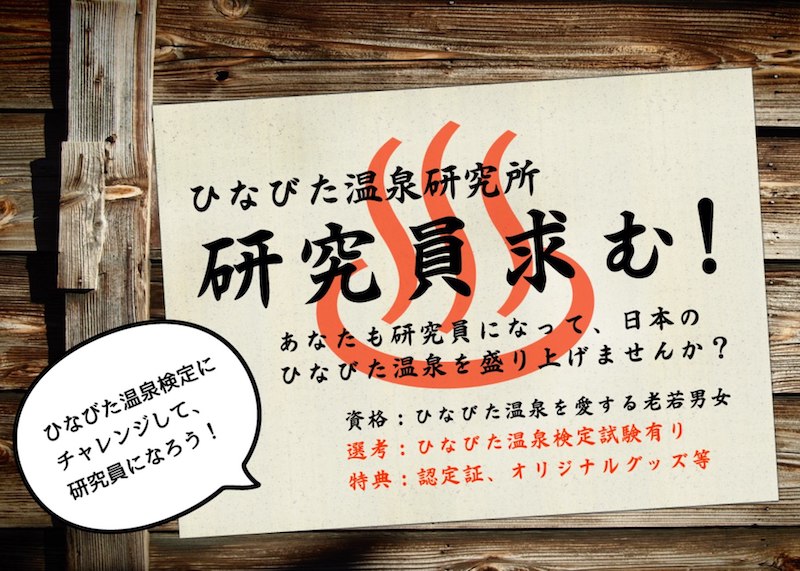室町。日本らしさの誕生。

「ここらへんは前の戦争で焼けちゃいましたから…」と京都人がいった場合、その「戦争」とは、第二次世界大戦ではなく応仁の乱のことであるとは、京都人たちのテッパンジョークだったりするけれど、ま、ジョークはさておいて、それほどまでに応仁の乱は京の都を焼き尽した壊滅的な戦乱だった。
でも、驚くべきは、そんな最中に、その後の日本文化に決定的な影響をあたえることになる「わびさび」という美意識が生まれたということだ。壊滅的な戦乱と美意識の誕生。ふつう、どう考えても相容れないはずなのに、なぜ「わびさび」は、そんなとんでもない時代に生まれたのだろうか。
その背景として、まず、ひとつは足利幕府が京都に開かれたということがあげられる。政治の中心地と、文化の中心地が一緒になったことによって、京都は室町幕府が置かれた二百年間にわたって、文化の発展を加速化させたのである。
鎌倉幕府も、江戸幕府も、あえて朝廷に一定の距離を置いた東国に開かれた。幕政は、そんなふうに距離を置いたからこそ、うまく、まわっていったけれども、文化は必ずしもそうではなかった。鎌倉が日本の最先端の文化発信地になることは決してなかったし、江戸が京都と張り合う文化の発信地になるまでには、実に百五十年もの年月が必要だった。こうしたことが証明しているように、文化の発展は、今も昔も都市が加速化させるものなのである。公家も、武士も、商人も、僧侶も、庶民も、農民も、芸能民もと…、さまざまな階級の者が混じりあう都市という舞台。そんな階級のるつぼの中で、化学反応がおきてこそ文化は想定外の方向に発展していくのである。室町幕府が京都に置かれたということは、つまりそんな意味をもっていた。
ふたつめの背景としては、鎌倉時代から室町時代にかけて、禅が根づいていったということ。それまでの仏教と違って、禅は「無常観」を説く仏教だった。この世の中に確かなものなんて、なにひとつとしてない。そんな禅の「無常観」は、明日をも知れぬ命を抱えながら、乱世を生き抜く武士たちの死生観に非常にフィットしたのである。そうして禅は武家や公家の生活に取り込まれていったことによって、和室のルーツである書院造りの建築や、茶の湯文化、能楽、水墨画の「余白の美」など、さまざまな文化や美意識として発展していった。なかんずく茶の湯は、禅の簡素な美を取り入れ、まさに「わびさび」誕生の場となって、やがてそれは、安土桃山時代に千利休により最強の日本文化にまで高められたのである。
ただ、そうはいっても茶の湯が「わびさび」に至るまでは、それなりの寄り道もあった。中国の禅僧が飲んでいたという茶が日本には奈良時代に“薬”として伝えられた。それが嗜好品となっていったのは、鎌倉時代から室町時代にかけてのことで、とくに室町時代には「闘茶(とうちゃ)」という茶を飲み当てるギャンブル的な遊戯として武家の間で大流行したのである。それは「わびさび」の茶の湯文化とはまったくかけはなれた世界でもあった。また、ド派手で奇抜な「婆娑羅(ばさら)趣味」も、このころに流行り、婆娑羅大名として名高い佐々木導誉(ささきどうよ)が開く茶会は、とりわけド派でなことで知られていた。彼が開く茶会の部屋は、豹や虎の皮や、唐物の茶器や美術工芸品が所狭しと飾られていたという、それはそれはゴージャスなものだった。そして闘茶の勝者には惜しみなく豪華な景品が与えられたのである。
しかし、何事もいきすぎてしまうと、振り子のように逆の方向に揺り戻っていくというのが世の中の道理というわけで、佐々木導誉に代表されるゴージャスで享楽的な茶会は、やがて、まったく真逆の「わびさび」の世界へと変わっていった。その契機となった人物が村田珠光(むらたじゅこう)だった。珠光はトンチの小坊主で有名な一休宗純に学んだ禅僧で、茶の湯と禅は同じ境地にあるという「茶禅一味」の考え方を打ち立てた。つまり、もともと茶の湯は禅から起こったものなのだから、その目指すところは禅と同じであるべきという考え方だ。珠光は、そんな考えのもとに、茶室をそれまでの広間から草庵の四畳半に変え、床の掛け物も豪華な唐物の美術品ではなく、禅の教えを説いた書に変えて、茶器も舶来品を無条件にありがたがる考えを戒め、唐物ではなく、国産の質素なものへと変えていった。こうして茶の湯は飲めや歌えやの享楽的なものから、もてなしの心を追求していく求道的なものになっていったのである。
しかしそれが世に広まっていくには、もうひとつ、大きな力が必要だった。室町時代といえば、茶の湯とならぶ代表的な日本文化である能楽が誕生した時代でもあった。能楽の誕生は観阿弥、世阿弥親子の功績にほかならないけれど、それを庇護した足利義満の存在無しではありえなかったといえるだろう。つまりパトロン的な存在が大きく左右したのである。同じように珠光からはじまった「わびさび」の茶の湯が広まっていった、その背景には、ひとりの権力者の存在が大きかった。それは誰か?足利義満の孫にあたる足利義政である。義政こそが「わびさび」の茶の湯をはじめとした、生け花や、和室、作庭など、日本文化の誕生を加速化させた巨大な磁場だった。将軍としてはかなり問題のある人物だったのだけど…
かつて銀閣寺には銀箔が貼られていたということが、まことしやかにいわれていたことがあった。金閣寺に象徴される足利義満の北山文化に対抗して、その孫の足利義政はギンギラギンな銀閣寺を建てたのであると。あるいは、銀箔を貼ろうとしたけれど、応仁の乱がもたらした財政難によってかなわなかったとか。
しかしそれは、いずれも間違っていた。銀閣寺に銀箔が貼られていなかったことは、その後の科学調査でも証明されたし、そもそも銀閣寺は慈照寺の俗称で、それは江戸時代になってから勝手にそう呼ばれるようになったに過ぎず、つまり、はなっから義政の頭のなかには「銀で対抗してやろう」なんて意識はなかったのである。
それでも金閣寺と銀閣寺は実に対照的な建築物といえるだろう。それは「金と銀」という、たんに表面的なことではなく、目指した方向性が対照的なのだった。義満が建てた金閣寺は三階建てで、一階は貴族の白木造りの寝殿造り風、二階は外装にだけ金箔が貼られているが、内装は質素な武家屋敷風、三階は外装にも内装にも金箔が貼られている中国風の様式。これには義満の野望が込められているという説がある。つまり「自分は貴族も武家も従えた中国の皇帝のような存在なるのだ」という野望が込められているいうのだ。真意はわからない。でも、明との国交において、天皇を差し置き、したたかに「日本国王」と名乗った義満ならば、いかにもありそうなことだろう。
一方、義政が建てた銀閣寺は権力の誇示などではなかった。そもそも義政は、権力を誇示するどころか、政治を放り出した、天下にダメ将軍として名を轟かせた人物である。応仁の乱は、義政の跡継ぎ問題に端を発してはじまった戦乱だったのに、義政はそれに背を向けて、自分の趣味である庭園や別荘造りに没頭した。世の中が大混乱になっているにもかかわらずだ。そして、その庭園や別荘造りの最高傑作が銀閣寺だったのである。将軍としてはダメダメだったけれど、美の探求者としては、義政は間違いなく、すぐれたセンスの持ち主だった。つまり銀閣寺は金閣寺のような権力の誇示ではなく、自分の美意識を満足させるためにつくられた、いわば彼の美意識の結晶だったのである。そしてまた、後に東山文化と呼ばれることになる、この銀閣寺を代表とした建築や庭園こそが、わび茶や生け花などの日本文化誕生の中心地となったのである。

義満の北山文化は豪華絢爛名世界。義政の東山文化は、それを反面教師にしたような寂びた世界。でも、目指す方向性がまったく違った義満の北山文化も、義政の東山文化も、サロン文化であるということでは共通している。サロン文化とは社交の場に生まれた文化である。そして、義満や義政が将軍だった室町時代、社交がとても大きな意味をもっていたのである。なぜか。それは乱世だったから。
足利家による室町幕府は、大げさにいうならば、乱世の上にかろうじて成り立っていた危うい幕府だった。「太平記」は後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕から室町幕府の誕生、そして南北朝の動乱の終わり頃までを描いた傑作軍記物語であるが、この物語をおもしろくしているのは、昨日の味方が今日の敵といった感じに、敵と味方がめまぐるしく変わっていくところで、それが読者を飽きさせないのである。なぜそんなにめまぐるしいのかというと、南北朝の動乱とは形こそ南朝と北朝の対立であっても、当の戦っている武士たちは自分の勢力を伸ばすことのほうが大切で、そっちに必死になっていたからである。そんなふうに「太平記」は乱世とはどんなものなのかをとてもよく伝えている物語なのである。で、話しをもとに戻すと、つまりは室町幕府とは、そんな、抜き差しならない状況の中に生まれた幕府なのだった。幕府という形をとっていても、その命令に従う大名はそれほど多くはなかった。つまりは、決して全国を支配していたわけでもなかったのである。
義満は、そんな南北朝の対立を、ほとんど詐欺みたいな手口で、南朝から三種の神器を取り上げて終わらせた。やりかたはどうであれ、半世紀も続いた内乱を、一滴の血も流すことなく終わらせてしまったのだから、やはり義満は並の政治家ではなかったというべきだろう。しかし、それで乱世が終わったわけではなかった。表面的な争いは終わっても、水面下の抜き差しならない状況はずっと変わらず、それは義政の時代になっても変わらなかったのだ。
さて、つまりは、そこでサロン文化がものをいう。戦乱とは政治的駆け引きが破綻して起こるものともいえる。戦乱はあくまでも最終手段であり、負けたほうはもちろん、勝ったほうだってたくさんのリスクを背負う、できれば避けたいものなのだ。だからこそ社交の場が重要な意味をもっていて、社交の達人であることが武士たちにとって大きな力となった。それは、たんに人あしらいがうまいということではなく、文化的な教養が問われるということでもある。この時代、もう、力だけの田舎大将は通用しない。力を持った守護大名たちは、こぞって文化教養度を高め、美術工芸品を収集し、京風の邸や庭園づくりに力を入れたのである。
義政の東山文化はそんなサロン文化の頂点に立つ最高の到達点でもあった。そこから生まれた茶の湯や生け花、和食、書院造りの和室、作庭などの日本文化は、いわば“おもてなしを主役にした芸術”でもある。たとえば能楽であれば、そこには舞台があって演者がそこで能を演じる。そしてそれを観劇する観客がいるわけである。あくまでも能楽が主役なのだ。ところが生け花の場合は、たとえば茶の湯の空間で、客の目を楽しませるための演出のひとつであるという位置づけであり、また、その茶の湯にしても、茶が主役なわけではないし、茶器が主役なわけでもないし、茶を点てる人が主役なわけでもない。茶を立てて、それをいただくという一連の時間を主人と客人が共有するという、その体験こそが茶の湯においての“作品”なのである。和食も、建築も、庭園も、おもてなしの時間の中で味わったり、目で楽しんだりするものである。義政の東山山荘は、そんなおもてなしの文化を生んだ場所であり、その後の日本文化の進む方向を決定づけた場所でもあったのだ。
乱世だったからこそ日本のサロン文化が発展していった。乱世だったゆえに、義政は政治がいやになって放り出した。でも、それが日本文化を生み出すきっかけになったのだから、おもしろいものです、歴史というものは。
※当サイトのすべての文、画像、データの無断転載を堅くお断りします。