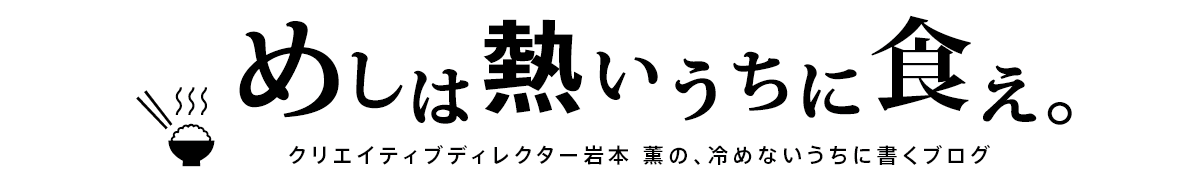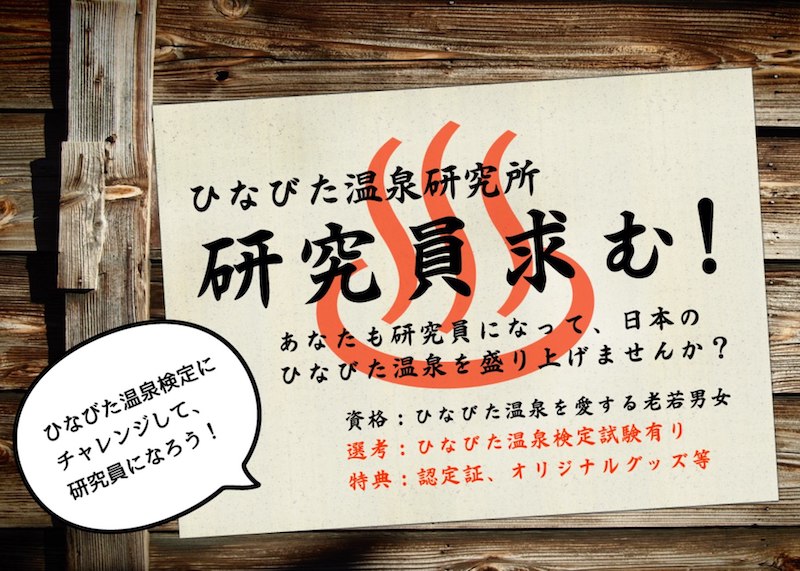消えていく音をつむいだ音楽/フェデリコ・モンポウ。

クラシックをあんまり聴かない人で、フェデリコ・モンポウって知ってます?って聞かれて「はい、知ってますよ!」って答える人って、そう多くはいないと思います。知る人ぞ知る、なんていうとちょっと大げさになっちゃうけど、大きなCD屋さんに行ってもほんの数枚しかモンポウ作品が置いてないってところが、事実を物語っているっていっていいのかもしれません。でも、現代のような、なんていうか心の余裕がなくなっているような今こそ、この汲み尽くしがたい希有な作曲家の音楽を聴いて、ココロのお洗濯をしてみるのも悪くはないんじゃないかと思うわけですね。
さて、モンポウです。この人はスペインのカタロニア地方出身の作曲家です。カタロニア地方といえば、ダリやガウディ、ミロ、カザルスといった偉大な個性派アーティストを生んだ土地でもあります。モンポウはそうしたビッグ・ネームに名を連ねても遜色はないっていうべきなんですけど、聞くところによるとかなり内気な人だったらしいんですね。そう、ダリのような派手でこれみよがしなパフォーマー気質とはまったく無縁の人だった。たとえばこんなエピソードがあるんです。それは彼が人生の岐路に立った18歳のころのこと。作曲家を目指していたモンポウが憧れてやまなかった人はフォーレだった。16歳のときに、はじめてフォーレのピアノをじかに聴いてからというもの、いつか自分もあんなふうな作曲家になろうと心に強く決めていたんですね。で、チャンスは早くも2年後にやってきた。モンポウの非凡な才能を認めていた地元の先輩音楽家が、フォーレが院長をつとめるパリ音楽院に紹介状を書いてくれたんです。そんなわけでモンポウは高まる胸をおさえ紹介状を手にして、“偉大なる心の師”に会いにいったわけですが、でも、けっきょくは会わずに帰ってきてしまった。理由は、怖くなってしまったから。待合室でフォーレを待っていたモンポウは憧れの作曲家に会うのが怖くなってしまって、こっそり逃げるようにしてパリ音楽院を後にしたんです。
こうしたモンポウの人並みはずれた繊細なところは、彼の実生活にどんな影響をおよぼしたかはわかりませんけど、ただ、作曲にはかなりプラスになっていたのかもしれません。「意識の水面に起こる静かな波紋のような」といわれるモンポウの音楽は、まさに繊細さの極北をいっています。それはたとえばワーグナーの音楽がスケールのでかい叙事詩とするなら、余計な装飾はなく、テーマの劇的な展開もない、シンプルな作風から生み出されるモンポウの数分たらずの小品は、その対極にある俳句みたいな音楽だっていえるのかもしれません。実際にモンポウ自身、日本の俳句に少なからずの関心をもっていたらしいんですね。彼がいったい誰のどんな俳句を好んでいたのか、かなり興味深いところでもあります。
アーティストにとって自分が生まれ育った環境は切っても切りはなせないカンケイにある。そんなわけでモンポウの母方の家系が代々、教会の鐘を作る職人さんだったっていうこと。だからモンポウが幼い頃から鐘の音色にごく自然に接していたっていうことは、これまた興味をそそることだったりします。いったいこの人はピアノの小品以外の音楽にはほとんど関心がなかったんじゃないかって思えるほど、ピアノの小品にこだわり続けた人でもあったわけで、その多くの作品はメロディよりも響きそのものに重きが置かれていた。余韻や残響といった、いうなれば“消えていく音”によって創られたような作品。それがモンポウの音楽なんですね。少年のころに聴いた鐘の音に不思議な感動をおぼえたというモンポウは、おそらくその鐘の音の響きの中に唯一無二の、なにか儚いものを聴いていたのではないでしょうか。音楽の建築性や空間性といったものとはあんまり縁のないモンポウの曲は、ときとして、諸行無常とでもいいたくなるような「瞬間であって永遠…」のようなものを感じさせてくれるわけで、そこがこの人の音楽の“ハマリどころ”だったりするんです。
そしてもうひとつ、モンポウの音楽を際立った個性として特徴づけていることとして、欠かせないのがカタロニアの民謡なんですね。ドビュッシーやフォーレ、サティといったフランス近代音楽に傾倒する一方で、モンポウはカタロニアの民謡を愛してやまなかった。フランス近代音楽の洗練とカタロニア民謡の土俗。これは普通に考えれば相反するものですよね。ところがモンポウの中では、それはぜんぜん相反するものではなかったわけです。さらにいえばその鮮やかな融合こそがモンポウ音楽の出発点だったっていえるのかもしれません。エスプリとプリミティブが同居しているとでもいいたくなるような、ちょっと不思議で素朴な味の音楽はまさにモンポウの独壇場です。たとえばモンポウはよくサティと比べられたりすることがあるわけですけど、サティとモンポウの大きな違いはそこにあるんですね。いっけんどことなく似たところがあっても、サティの音楽からはそういった素朴さは感じられない。彼の場合はもっと曲者でアイロニカルです。モンポウみたいに“純粋”ではない。まあ、それはそれですごく味わい深くてナイスなところなんですけど。サティとモンポウ。ともあれ二人ともプリミティブなピアノ小品のずばぬけた名手であるわけで、聴き比べるととてもおもしろい二人だったりするわけです。
その時代に名を馳せた作曲家を指して、次の世紀にはこういう人は現れないでしょう、なんていいかたは、思えばけっこう誰にでもあてはまることだったりします。でもモンポウについてはあえてそんなことをいってみたくなるんですねえ。いとおしくなるような時代の希少価値みたいなものををひしひしと感じさせてくれるんですから。さて、そんなわけで、まとめとしていうなら、ふりかえると現代のシリアス音楽はシェーンベルクの調性の破壊で幕開けて、それからめまぐるしい変化を遂げてきたわけですね。やれ偶然の介在だ、やれセリー主義だ、ミニマルだ、サンプリングだ、ノイズだと、なんだか、あれこれといろんな手法が徹底的に推し進められた時代だったわけで(それはそれで刺激的でおもしろかったけど、今はもう疲れちゃうっていう気もしないではないわけでもあって)、じゃあ、これかはもっともっとそんなことが加速していくのかっていうと、どうやらそうでもなさそうでもある、と。え~、なんていうんだろう、そう、単純にヒーリングとか原点回帰とは違う意味で、脱ロジカルなスピリチュアルなモードにシフトしているような感じなわけだったりして、で、となると、モンポウの音楽なんかは、これからもっとおもしろい位置づけにあった音楽として、改めてクローズアップされてもいいんじゃないか、されるべきなんじゃないか、って気がしてくるわけです。
さてさて、そんなモンポウのおすすめCDはというと、
「カタロニアの影/モンポウ・ピアノ曲集」
ジャン=フランソワ・エッセール
60年近くにわたって、おりにふれて書きつづられた連作「歌と踊り」は、モンポウのライフワークだったっていえるのかもしれない。なかでも第5番は、なんともモンポウらしくまるで夢の向こう側から聞こえてくるような浮世離れしたリリシズムをたたえているんですけど、実はこの曲、実際モンポウが夢で聴いた音楽を枕元の五線譜に書き留めたものがモチーフになってるんですね。夢の中のモンポウが、どんなシチュエーションで、どのような音楽を聴いたのか(つまり夢の中で聴いた音楽がどこまで忠実にこの作品にいかされているのか…)なんとも気になるところですけど、ハイ、歌と踊りの第5番、これは必聴です。
「モンポウリサイタル」
アリシア・デ・ラローチャ
「悲しい鳥」を聴いてみましょう。儚く、ちょっとしたデジャ・ヴュさえも覚えずにいられないこの小品を、モンポウのベストっていう人、少なくはないと思います。こんなにシンプルなのに、何度聴いても飽きない。汲み尽くしがたいモンポウ音楽の本領発揮といったところです。「悲しい鳥」っていうタイトルからして、とても詩的でいいですね。「私の作品の怖ろしいほどの見事な演奏者」ってモンポウ自身にいわしめた、いわば本人お墨付きのピアニストがラローチャ。クラシック界ではピアノの女王という呼び名をいただいているのがラローチャであるわけですけど、やっぱり彼女の魅力は祖国スペインの音楽において最大限に発揮される。ラローチャの申し分のないタッチで、モンポウ音楽の詩情をしみじみと堪能してみてください。
「ひそやかな音楽」
ヘルベルト・ヘンク
28曲の小品からなる「ひそやかな音楽」は、いわばモンポウの自己探求の集大成。その多くがあくまでも自分のために書いた曲であって、そのためか当時は楽譜を出版することさえためらったといいます。原題は“MUSICA CALLADA(ムシカ・カリャーダ)”。直訳すれば「沈黙した音楽」とか「音のない音楽」とかになるんですけど、ああ、まさにモンポウの音楽そのものじゃないですか。これはモンポウが傾倒するルネッサンス期スペインの詩人の詩句からとったそうです。ひそやかに、もっとひそやかに。本質は表面じゃなく余韻にあるんだよ、と、そんなことをそっと教えてくれるような一枚です。現代音楽のスペシャリスト、ヘンクが見事に聴かせてくれますよ。