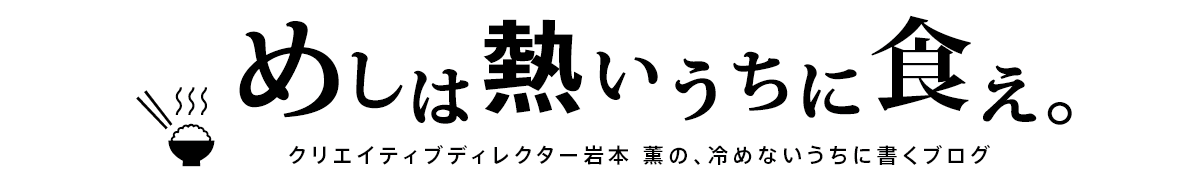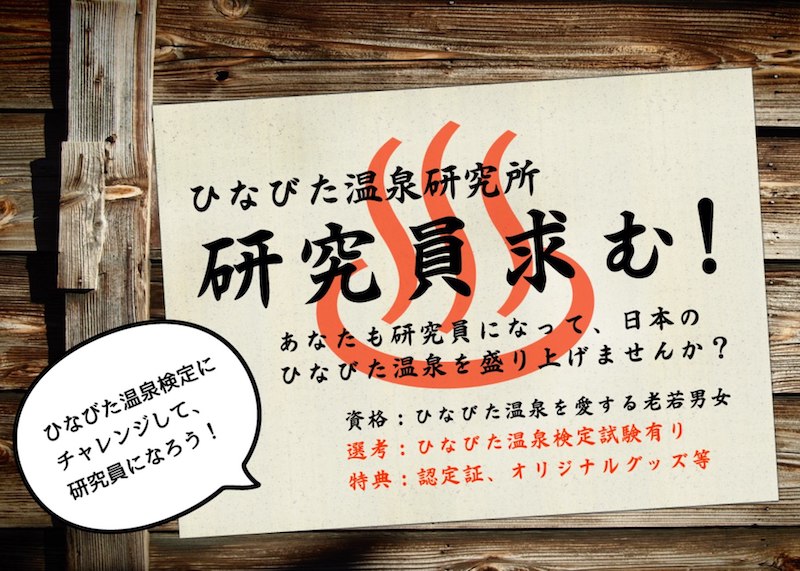ニーナ・シモン。ニーニャがニーナになるまでに。

少女時代、彼女は“ニーニャ”と呼ばれていた。近所の仲がよかったヒスパニック系の男の子が彼女のことをそう呼んでいたのだ。“ニーニャ”とはスペイン語で小さな女の子を意味していた。彼女はそのあだ名がとても好きだったし、とくに“ニーニャ”という、その言葉自体の響きが気に入っていた。そんなことから懐かしい少女時代の思い出をこめて彼女は自分の芸名をニーナ・シモンとした。シモンは、当時、憧れていたフランス映画の女優シモーニュ・シニョレからとった。
彼女が自らそんな芸名をつけたのは、あんまりパッとしない本名のユーニス・ウェイマンという名前がいやだったからではなかった。そうではなく、ナイトクラブのピアニストとして(それも酒びたりのアイルランド系の老人たちの吹きだまりみたいなバーのようなナイトクラブの)ステージに立つなんてことが、敬虔なクリスチャンである母親にばれたりしたら、大変なことになるからだった。でも、幸いにも身内の誰にもばれることなく、初日のステージを終えて、不本意ながらも一応“プロのピアニスト”として、その日のギャラを支配人からもらうとき、彼女はある決定的なことをいい渡された。
「ニーナ。とてもよかった。気に入ったよ。でも、問題がなかったわけじゃないんだ」支配人はいった。「この店がなにを必要としているのか考えてみてほしい。ステージでなぜ歌わなかったんだ?」
「私はピアニストですから、歌は歌いません」
「わかった、オーケー。ニーナ。それなら、明日から歌手になるか、クビになるかのどっちかだ」
 人生はひょんなことから思いもよらない方向にシフトする。でも、そういうのって、それほど珍しいことではありませんね。ただ、ニーナ・シモンの場合のそれは、レベルが普通とはちょっと違っていたっていうべきかもしれません。彼女にそうしたひょんな転機がおとずれたのは、彼女がまだ黒人初のコンサートピアニストという大きな夢を追いかけていた21歳の頃だった。
人生はひょんなことから思いもよらない方向にシフトする。でも、そういうのって、それほど珍しいことではありませんね。ただ、ニーナ・シモンの場合のそれは、レベルが普通とはちょっと違っていたっていうべきかもしれません。彼女にそうしたひょんな転機がおとずれたのは、彼女がまだ黒人初のコンサートピアニストという大きな夢を追いかけていた21歳の頃だった。
当時のアメリカに暮らす、たいていのアフロアメリカンがそうだったように、ニーナもまた、アメリカ南部の田舎町で生まれました。音楽好きだった家族の中で育った彼女は、物心がついたときにはもう呼吸するのと同じぐらいに、ごく当たり前に音楽を楽しんでいたといいます。だから、すでに2歳の頃には家のオルガンで好きな賛美歌を堂々たる弾きっぷりで弾くこともできたし、近所の教会に通える歳になったときには地元の教会の“小さな専属ピアニスト”として立派に活躍していた。そんな彼女のことをまわりの大人たちは神童と呼び、この評判はいつの頃からか、この町から黒人初のコンサートピアニストを誕生させるという、町の人々の夢に変わっていって、ついには「ユーニス・ウェイマン基金」なんてものまでできてしまった。ニーナの家庭は比較的裕福ではあったけど、それでも本格的な教師をつけてピアノのレッスンをするとなると、普通の黒人家庭ではとうてい無理な話しだったんですね。だから町のみんなでお金を出し合ってニーナに本格的なクラシックピアノの教育を受けさせたんです。もちろんニーナ本人にとってもコンサートピアニストは想像するだけでうっとりとするエレガントな夢だった。まわりの年ごろの女の子たちの話題にのぼる、おしゃれのこととか、ダンスパーティのことや、男の子のことにも興味がなかったわけではなかったけど、でも、あくまでも自分の夢はアーティストとして腕一本で生きていくピアニストである。カーネギーホールのステージであふれんばかりの拍手を受ける黒人初のコンサートピアニストは、自分が“そうなるべき姿”にほかならず、そうなるためには、遊んでいる暇なんかなかったわけなんですね。
そうして、まっすぐと夢を追いかけたニーナは、1日平均5時間ピアノを弾いて、なおかつ学業もおこたらず、ひたすら頑張った。で、その努力が報われて、ハイスクールはトップクラスで卒業、そして晴れて奨学生としてN・Yのジュリーアード音楽院で学べるチャンスを手にしたんです。奨学金がもらえる1年間、ジュリーアードでみっちりとピアノを学び、さらにフィラデルフィアの名門カーティス音楽学校の奨学金試験を受けるべきだ、というのが両親をふくめ、ニーナを支援する人たちの意見だった。名門カーティスで学んで、6歳からの夢をいよいよ現実のものに。そう、夢はもう手の届くものになろうとしていた、と…。ところが人生はそう思い通りにいくものではない。ここでニーナは最初の挫折を味わってしまうんですね。カーティス音楽学校の奨学金試験を受けたニーナのもとに届いたのは、彼女が考えてもみなかった不合格通知だったんです(この不合格については人種差別によるものという説が強く、それは後に彼女が60年代米国のキナ臭い公民権運動へと身を投じていく要因のひとつにもなっています)。
さて、カーティスを落ちてしまったニーナはどうしたのか。ここで話しは冒頭へとつながっていくんです。当時の彼女のショックは、まさに目の前が真っ暗になるといったような深くやりきれないものだったけど(このあたりは「ニーナ・シモン自伝」に詳しいので、興味のある方は読んでみてください)、彼女は夢をあきらめなかった。その頃にはすでに底をつきそうになっていた「ユーニス・ウェイマン基金」で、本来なら自分の担当教授になっていたかもしれないカーティスの教授からピアノの個人レッスンを受け、ふたたび夢を追い求めたんです。でも、やはりお金がネックになったんですね。自立した生活と充実したレッスンを両立させるためには普通の仕事じゃ、とてもやっていけなかった。そこで偶然、実入りのいいナイトクラブの仕事を知って、彼女は決心してそのステージに立つことにした。でも、そう、それはあくまでもピアニストとしてではなく、弾き語りの歌手としてだった…。
ひょんなことから弾き語りの歌手としてナイトクラブのステージに立つことになったニーナの人生は、ハイ、ここから一気に加速しはじめます。それまでクラシック音楽こそが“自分にとっての本物の音楽”と信じ、どちらかというとポピュラーソングを見下していた彼女は、やむなくポピュラーソングを歌いました。でも、やっぱり自分が納得できる歌い方をしたかったんです。そんなわけで彼女はポピュラーソングをできるかぎりクラシック風にアレンジして深みのある音楽に仕立てて歌ったんですね。具体的にいえば、クラシックのモチーフを組みあわせてインプロヴィゼーションし、ゴスペルやブルースの要素も取り入れて…、と、なんだか、ありそうでなかった魅力的な独自の音楽をつくりだした。で、これが実にウケたんですね。評判は口コミでまたたく間に広まって、ひと月もするとニーナの存在は町中に知れわたるようになった。いつしか店の客も酒びたりのアイルランド系の老人たちから、音楽を熱心に聴きに来る若い学生たちに変わって、もちろん連日連夜の大繁盛。ニーナ自身も、そういうふうにポピュラーソングをアレンジしていくうちに、クラシックと、それ以外の音楽という線引きにあまりこだわらないようになり、逆に自分自身から生み出されていく何かをカタチにしつつある、と感じられるようになっていったんです。
町の評判はやがてまわりの州へと飛び火して、ニーナは東海岸のあちこちのクラブでの人気シンガーとなりました。こうなると、もう、次はレコーディングですね。最初のレコーディングは、今やモダン・ジャズ最後の聖域と呼び名の高い、あのベツレヘム。このレコーディングにあたってはベツレヘムの社長シド・ネイサンが直々にニーナの家にやってきて、収録するナンバーのリストを彼女に見せたりしたんですけど、ニーナはあっさりとそれを無視して「自分のアルバムの曲は自分で選ばせてほしい」といいわたしてネイサンを仰天させたりしています(痛快ですよね)。そんなわけでニーナのファーストアルバム「リトル・ガール・ブルー」の収録曲は当時彼女がクラブで歌っていたレパートリーからセレクトされているんですね。で、このアルバムからシングルカットされた「アイ・ラブズ・ユー・ポーギー」が東海岸気全域で大ヒットして、ニーナの名はさらに広く知れわたることになる。そうしてスターへの階段を登りはじめたニーナはベツレヘムからコルピックスへ移籍して2枚目のアルバム「アメイジング・ニーナ・シモン」リリースし、またクラブギグからホールへと進出して、ニューヨーク・タウン・ホールでコンサートを開いて大成功を収めるんです。ニューヨーク中のマスコミを熱狂させこのコンサートによって、その名は海外にも知れわたり、さらにそれから5年後、そのころには、すっかりメジャーシンガーの仲間入りをはたしたニーナは、ついにあのカーネギー・ホールの、そう、本人いわく「私がユーニス・ウェイマンだったころから死ぬほど憧れ続けた夢でもあった」ホールのステージに、フルオーケストラをバックに従えて立つことになるんです。ああ、もうニーナの人生は止まらない…
 え~、いかがでしたでしょう。“ニーナ・シモンが本物のニーナ・シモンになるまで”のいきさつを、ざっと話すとこんな感じになるんですけど、なんていうか、才能のある人の人生っていうのは、世間が放っておかないっていうか、ちょっとしたきっかけで一気に華開いてしまうんですね。たとえそれが本人が望んでいない方向であっても…デス。実際、ニーナはシンガーとして成功してからもしばらくはクラシックピアノのレッスンを続けていてコンサートピアニストの夢を追い続けていたりします。「誰かが自分に十万ドル寄付してくれたら、さっさとポピュラー音楽を捨ててジュリアードに入学していただろう…」と自伝でも語っていたりするわけで、あんなに人の心をゆさぶる音楽を世に送りだしておきながら、本人はいたって醒めているみたいなところが(いや、醒めていたかはわかりませんけど)、なんかおもしろいんですね。ひょんなことから違った方向へシフトしてしまったニーナの人生。う~ん、というよりも、彼女自身が自分の人生を変えてしまうヴォイスをもっていたっていったほうがしっくりくるのかもしれませんね。
え~、いかがでしたでしょう。“ニーナ・シモンが本物のニーナ・シモンになるまで”のいきさつを、ざっと話すとこんな感じになるんですけど、なんていうか、才能のある人の人生っていうのは、世間が放っておかないっていうか、ちょっとしたきっかけで一気に華開いてしまうんですね。たとえそれが本人が望んでいない方向であっても…デス。実際、ニーナはシンガーとして成功してからもしばらくはクラシックピアノのレッスンを続けていてコンサートピアニストの夢を追い続けていたりします。「誰かが自分に十万ドル寄付してくれたら、さっさとポピュラー音楽を捨ててジュリアードに入学していただろう…」と自伝でも語っていたりするわけで、あんなに人の心をゆさぶる音楽を世に送りだしておきながら、本人はいたって醒めているみたいなところが(いや、醒めていたかはわかりませんけど)、なんかおもしろいんですね。ひょんなことから違った方向へシフトしてしまったニーナの人生。う~ん、というよりも、彼女自身が自分の人生を変えてしまうヴォイスをもっていたっていったほうがしっくりくるのかもしれませんね。
さてさて、じゃあ、そんなニーナ・シモンのおすすめを3つ、ご紹介。
なんでこの人の弾き語りは、
こうまでも心を直撃するんだろう?
そう思わずにいられない孤高の大名盤。
「ソウルの世界~ニーナとピアノ」
「私にとって“ジャズ”とは考え方や生き方のことだった。あるいは歩き方、話し方、考え方、行動のとり方など、アメリカの黒人がすることすべてを意味した。つまり“ジャズ”とは黒人全体を見渡した場合のある一面であり、その点では黒人である私をジャズ・シンガーと呼んで問題はないとは思う。だが、ほかのあらゆる面で私はジャズ・ミュージシャンではなかった…」というのは既存のジャンルでくくられることを嫌ったニーナ本人の言葉。「どうしてもなにかのジャンルに分けなければならないなら、フォーク歌手とされるべきだと思う。私の音楽にはジャズよりフォークやブルースの要素が多かったからだ」
ニーナの音楽を聴くのは“ひとつの特別な体験”である、なんてふうにいわれています。この、いかにも大げさなものいいが、大げさに感じなくさせてくれるのが、このアルバムだったりします。「私はジャズ・シンガーではない」というニーナの言葉もこれを聴けばきっとわかるはず。収録ナンバーが純粋なピアノの弾き語りのみということもあって、彼女のエモーションが手に取るように直に伝わってくるんですね。なんていうかか、それは確かに“孤独”なんだけど、触れていて心が落ち着くような孤独。そんな不思議な孤独が伝わってるるんですね。ニーナが辿り着いた孤高の世界です。「ん?」って感じのセンスの邦題とジャケットデザインにまどわされてはいけません。中身はほ~んとすばらしいんですからね。弾き語りなので、彼女のピアノもたっぷり楽しめる大名盤。
この1枚がニーナの人生を決定づけた!
名唱「アイ・ラブズ・ユー・ポーギー」を聴きましょう。
「リトル・ガール・ブルー」
たとえばフィッツジェラルドの小説だとか、エドワード・ホッパーの絵だとか、なんていうんだろう、派手な繁栄と哀しみがいつも表裏一体のアメリカでなければ出てこなかった琴線に触れてやまないものがかつてはあったわけで、ガーシュインの音楽なんかもまた、その最たるものじゃないかって思うわけです。で、そのガーシュインの名曲「アイ・ラブズ・ユー・ポーギー」の決定的な名唱が聴けるのが、このニーナの記念すべきデビューアルバムなんですね。「アイ、ラブズ、ユ~、ポォ~ギィ~」という出だしを聴いただけで、ああ、これは違うゾってわかる名唱です。たまりません。それにしても本文でもふれましたけど、クラブまわりをしていた当時のニーナはこんな感じに歌っていたんですね。そりゃあ評判になりますよねえ。ニーナが歌うようになってからお店の客層が変わってしまったっていうのも、これを聴けば納得。「リトル・ガール・ブルー」も負けず劣らずの、文句なしの名唱です。イントロのピアノからして素晴らしい。つまりこれが彼女のいうクラシック風アレンジだったりするわけで、さすが伊達じゃないです。
アーシーでソウルフルな、
ニーナ入魂のズシリとくる1枚。
「ニーナ・シモン・シングズ・ザ・ブルース」
これは、アーシーな1枚。そう、黒いです。ちょうど時期的にも、「ブラック・イズ・ビューティフル」のスローガンのもと激しく繰り広げられた公民権運動真っ只中の頃だけあって、曲のセレクトも意識的なところがあったのかもしれません。60年代後半の黒人音楽のテイストが色濃くでています。ブルージーで、ソウルフルで、まさにニーナならではのズシリとくる聴きごたえのあるアルバムっていうべきでしょう。それにしてもうまいですねえ。エモーションが見事に伝わってくる。なかでも、すばらしいのが「あの人は死んでしまった」。これまた「ポーギーとべス」の中からのガーシュイン・ナンバーだったりしますけど、いや、たまりませんね。こんなふうに歌われてしまうと。「アイ・ラブズ・ユー・ポーギー」に並ぶ名唱。自作曲も5曲入っていて、ソングライターとしての彼女の才能もうかがえます。