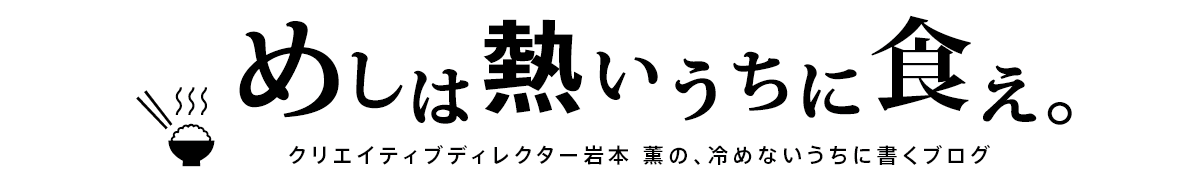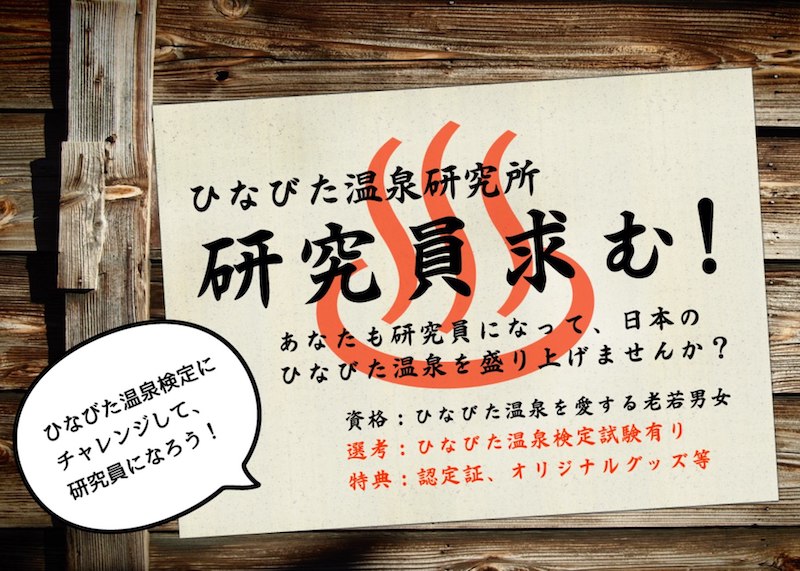元信の昇天

狩野派といえば、説明するまでもない、室町から江戸にかけて幕府の御用絵師としてつかえた名門の絵師集団である。始祖である狩野正信が足利家の御用絵師としての道すじをととのえ、二代目の元信がその実績を確たるものとして、四代目の永徳が信長や秀吉といった希代の天下人たちの心をつかんで、御用絵師集団としての揺るぎない地位をかためた。これから語る物語は、その二代目の元信にまつわる、ちょっとした伝説である。
足利家の何代目の公方様であったかはさだかではない。ある晩のこと、公方様の夢枕に天狗が立った。鞍馬山の名高い大天狗である大僧正坊だった。 儂の姿を絵に描いてほしいのだ、と大僧正坊はいった。絵師は狩野元信源信がよかろう。手みじかにそうつげて煙にように消えたのだという。
翌朝のこと、さっそく狩野元信のもとに、将軍家からの使いがやってきて、ことの一切合切をつたえた。元信にとって将軍家は狩野家の大きな後ろ盾であったから、断るわけにはいかなかったし、鞍馬山に奉納する絵であれば元信にとってもそれは悪い話ではなかった。むしろ、このうえない話というべきものだった。しかし、ひとつだけ気にかかることがあった。それは元信が大天狗大僧正坊の姿を見たことがないということだった。
ただ、この時代、龍や獅子なんかがそうであったように、絵師が見たことのない架空の生き物を描くことは珍しくはなかった。元信にしても、そうした架空のものは、いくども描いてきている。そしてまた、天狗もそうした架空のものとして、多くの絵師によって描かれてきていたのだった。
しかし、それが鞍馬山の大僧正坊となると話が違った。鞍馬山の大僧正坊といえば天下に名を轟かす大天狗なのだ。そんじょそこいらの天狗とは格が違った。これまでのような凡百の烏天狗の姿で描くわけにはいかない。誰も見たことのないような、威厳に満ちた姿でなければならない。しかも公方様の夢枕に立った天狗なのである。はたしてそれは、どのような姿であるべきなのか?そもそも大僧正坊の姿を見たことがある者など、誰もいなかった。見たことがない姿をいかに描けばよいのか?
そうして元信の苦悩がはじまった。
俺には描けない。龍にせよ獅子にせよ麒麟にせよ、それらは大陸から渡ってきた手本があってこそ描けたのだ。手本もなにもないものを、しかも公方様の夢枕に立った大僧正坊の姿を、どうして俺に描けるのだろうか。
元信は、思いつく限りの文献にあたってみた。あらゆるつてを頼り、名刹の高僧から、得体のしれない念仏坊主までをたずねて、高名な大僧正坊とはいかなる姿であるべきなのかを訊いてみたものだった。しかし、誰ひとりとして答えてくれる者はいなかった。いったい、かの大天狗の姿を、私ごときがどうして答えられるのだろうか、と。
奉納の時はこくこくと迫ってきた。春の花供養の頃には間に合わせてもらいたい。使いの者達はそういっていた。しかし季節はすでに新しい年を迎えてかなりの日々が過ぎていた。それなのに、元信にはなすすべもなく下絵すら手がけていなかった。俺には描けない。しかし、こうも時が過ぎてしまっては、もう断ることもできまい。なぜ俺はこんなことを引き受けてしまったのだろうか。
悩みつづけたある晩のこと。
元信は鞍馬寺の山門へと続く石段を登っていた。月があたりを青く照らす満月の夜だった。つづら折りの参道を登りながら、元信は自分のことを呼んでいるかのような不思議な力を身体で感じていた。
気がつくと視界がひらけたところにでて、そこに鞍馬寺の山門があった。元信は閉じられている山門の前に立ちつくした。月明かりが閉まった門に元信の影をゆらゆらと映し出していた。辺りはひっそりと静まり返っていた。
しばらく、見ることもなしに門に視線をやっていた元信だが、微妙な変化に気がついた。影が少しずつ形を変えていったのである。最初は影全体がぶよぶよと震えるようにゆらめいていた。しだいに肩のあたりから鷲のような大きな翼が生えてきた。徐々にそれは高下駄を履いた山伏のような姿となっていき、やがて仁王立ちするかのような威厳のある影となって山門に映しだされていた。顔にはへちまのような奇妙な鼻が突き出ていた。
はっと気づいた元信はきびすを返して一目散に自分の工房へと走った。工房に戻るやいなや、行灯の火を灯して、すぐさま紙にむかった。それからひと月もの間、まともな食事も睡眠も取らずに憑かれたように大僧正坊の姿を描いた。
出来上がった大僧正坊の絵は無事、春の花供養の前に将軍に献上され、鞍馬寺へと奉納された。 奉納から数日たったころに、元信のもとに将軍の使いがやってきて、金子とともに高価な絹の反物が褒美として贈られた。将軍に大僧正坊の絵を献上した元信はたちまち世間の評判を集めて絵師として名を挙げていった。天狗の姿は、これまで烏天狗の姿でしか描かれなかったが、元信の筆による大僧正坊の姿は、背中には鷲のような巨大な羽をはやした異形の山伏姿で、なによりも世間を驚かせたのは、その赤銅色の顔の真ん中に、へちまのような巨大な鼻が突き出ていたことだった。この絵が描かれて以来、格の高い天狗の姿は、いずれも大僧正坊の姿のような、へちまのような巨大な鼻をもつ顔で描かれるようになったのだという。
それからの元信が当代随一の絵師としての名声を博したことは、後世につたえられているとおりである。元信はその類まれな筆の力で、幕府の御用絵師としての地位を盤石なものとして、四百年もの長き時代にわたって画壇に君臨し続けることになる狩野派の礎を築いた。
しかし古今東西の芸術家たちが老いとともに、やがてその神通力を衰えさせていくように、元信もまた、老境へはいっていくなかで、かつて名声をほしいままにしてきた、その筆の力を失っていったのである。狩野派としては、後を継いだ三男の松栄が凡庸な絵師であったものの、その松栄の息子の永徳が、あたかも松栄の穴埋めをするかのような、まぎれもない天才だったため、元信としても、狩野派の行く末を心配せずにすんだ。永徳は俺をはるかに超える絵師になるだろう。元信はそんな永徳のことをいたく可愛がったが、その影で元信自身の絵師としての名声は完全に過去のものとなっていた。
時は永禄二年。尾張の国主となった織田信長が、軍勢を率いて足利義輝に謁見した年であった。時代は大きく動こうとしていた。
元信は鞍馬寺の山門の前に立っていた。いまいちど、筆の力をとりもどしたい。そんな切実な思いが元信の老いた足をここまで運ばせたのだった。かつて大僧正坊の姿を描けずに苦悩した元信が不思議な力に導かれて鞍馬寺の石段を登っていった、あの晩とおなじような満月の晩だった。忘れたことなど一度としてなかった。この山門に映しだされた自分の影が姿を変えていったあのときの、身体が溶けていくかのような奇妙な感覚と、恍惚感を。
立ちつくして山門にゆらゆらと映し出された自分の青い影を凝視する元信の前で、それは起こった。あの晩と、まったくおなじだった。影が震えるようにぶよぶよと少しずつ形を変えていった。そうして背中に鷲のような巨大な羽をはやした異形の山伏姿のような影へと変わっていった。顔にはへちまのような奇妙な鼻が突き出ていた。
名状しがたい恍惚感に包まれながら、なおもその青く震える影を見つめていると、鷲のような巨大な羽がゆっくりと羽ばたきはじめた。
気がつくと元信の身体は宙に浮いていた。それからみるみるうちに天高く舞い上がっていき、ついには芥子粒のような点になり、やがて、漆黒の夜空に吸い込まれるように消えていった。