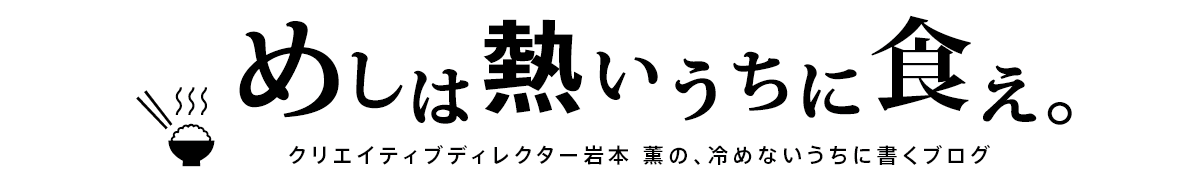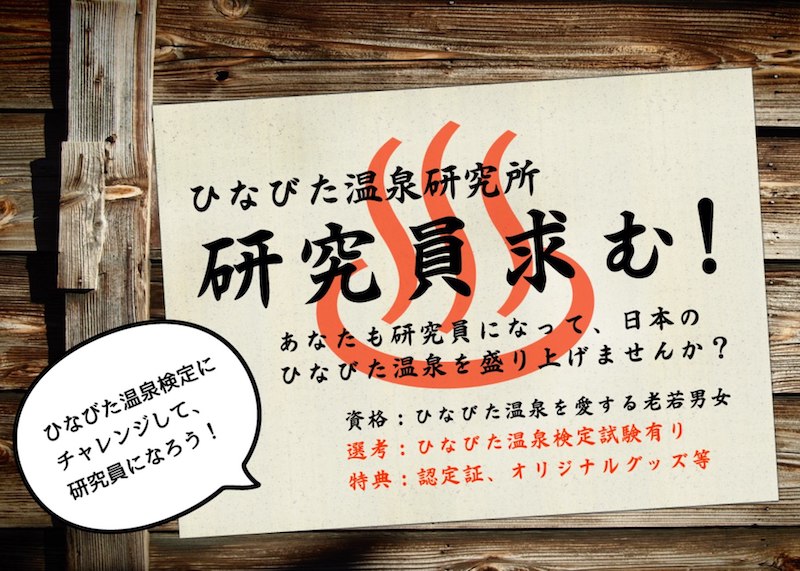物欲が世界から消えつつある?/「物欲なき世界」
もう欲しいモノは別にないような気がする…
管付雅信氏の「物欲なき世界」のまえがきは、映画監督のペトリ・ルーッカイネンのそんな言葉からはじまり、そして、こう続く。実はほとんどのモノがなくてもかまわないということに気づいたんだ。そしてモノに圧迫されていた環境から解放されて、それがすごく幸せに感じた。そう、現代において、消費は一種の中毒であり病気なんだ。
人はどこまでモノを買わないで生きていけるのか?そんな実に興味深い試みを、自らが主演をつとめて映画にしたペトリ・ルーッカイネン監督の「365日のシンプルライフ」(http://www.365simple.net/)は、自分のアパートメントにあるモノをすべてを倉庫に預けて、そこから1日ひとつだけ必要なものを持ち帰っていい、買い物は食料以外はいっさい買うことを禁じる、と、そんなルールを課して、実験的に1年をすごしたドキュメンタリー映画である。
1日目、空っぽの部屋から必要なモノを取りに倉庫へ向かったペトリは当然モノをなにひとつ所有していない。もちろん服もだ。そんなわけで新聞紙で前を隠しながら全裸で倉庫目指してヘルシンキの街を駆け抜けていった。で、最初に持ち帰ったものは、なんだったのかというと…ロングコートだった。パンツではない。コートなら身にまとえば外を歩けるし、家に帰っても寝具代わりにもなるからだ。
そんなふうにペトリは毎日、毎日、自分に課した奇妙な苦行の中で、ほんとうに必要なモノはなんなのか?いったい自分はなんのためにたくさんのモノをもっていたのか?…等々、自問自答を繰り返し、やがて、冒頭のように「実はほとんどのモノがなくてもかまわない」ということに気づいて、消費は病気であるとの結論に至るのである…
「今、先進国では物欲が減りつつあるのではないか?」。本書はそんな著者のもやっとした実感から書かれはじめた。日本では若者の消費離れがいわれるけれど、それは日本の若者だけのことではなく、先進国の先進都市で一様に起きている現象なのではないか?そして、それはたんなる世界不況とか消費疲れといったネガティブなことだけではなくて、先進国の先進都市だからこそ真っ先に突き当たった、次なる社会に脱皮するためのサインなのではなかろうかと。
さて、この本の著者が、経済やマーケティングの専門家ではなく、編集者であるということにもぼくは注目したい。時代の空気に敏感にならざるをえない編集者、しかも「コンポジット」「インビテーション」「エココロ」などの編集長を務めてきた高感度な編集者なのである。時代がゆっくり大きく変わっていくさまを敏感にキャッチするのは、データや理論の専門家よりも、人の欲望や好奇心と常にがぶりよつで対峙してきた編集者のほうではないだろうかと、ぼくは思う。
ほしいモノがだんだんなくなってきた、という感覚はたぶん、みなさんも普通に感じているのではないかと思うけど…どうでしょう、違いますか?それもそのはずで、物欲の多くの部分は第三者によって無理くりつくりだされてきたものだ。マーケティング、ブランディング、広告キャンペーン、メディア等々。より新しいモノへ、より便利なモノへ、より見たことないモノへと。でも、世の中はもうモノであふれかえっている。さらにはモノに加えて、スマホに代表されるような、情報機器の情報に縛られて、なんともスカッとしない息苦しい時代になっている。だからこそ、本書が、ポートランドをはじめに、世界の先進都市で起きている新しい時代の兆候のようなものを紹介しながら、脱経済至上主義的な次なる社会の姿を浮かび上がらせようとしているところに、希望を感じてやまない。ああ、今の息苦しいようなこの状態はやがて終わるのかもしれないなぁ、と。
著者はこういう。資本主義はいつまでも続かない。私たちの孫世代は「かつて資本主義というものがあった」という話をすることになるだろう。そして彼らは「セックス・アンド・ザ・シティ」の主人公たちのブランド品への狂おしい執着を、さっぱり理解できなくなるに違いない、と。