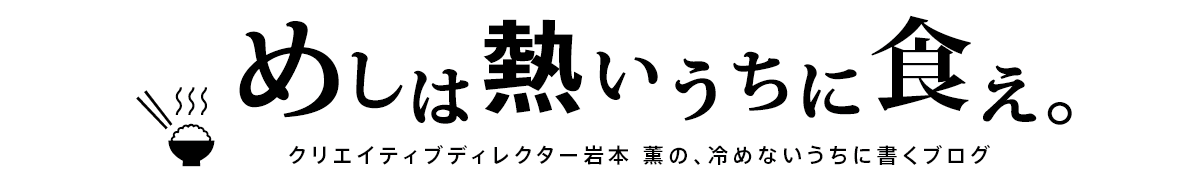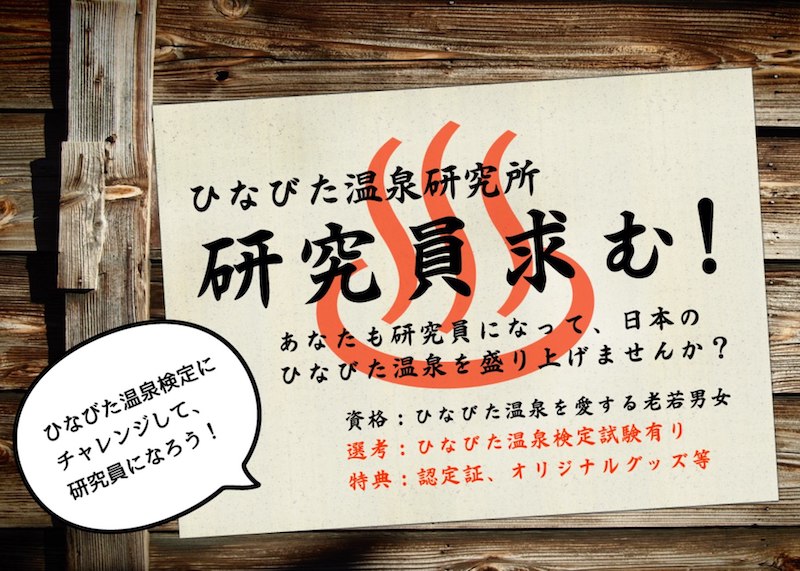聖も俗も超越してそこにある富士山。
女性が自殺しようと樹海の付近に来たのは、その日の午後の二時前後のことだった。空は曇っていた。女はためらうようにその場で二時間くらいを過ごした。意を決して歩きはじめると、いつの間にか日差しが出ていて自分の影が地面に長く伸びていた。なにげなく見上げると、巨大な山が目の前にあった。(「なにも願わない手を合わせる/富士を見た人」藤原新也)
霧が晴れていきなり目の前に現れた真っ白い富士山。自殺しにきた彼女には、なぜかそれが自分を抱きしめてくれる、とてつもなく大きな人の心のように感じられたのだという。彼女はそこで泣き崩れた。しばらく涙が涸れるまで泣いてから、ふたたび見上げると、富士は夕日に真っ赤にそまっていた。彼女は富士に笑いかけ、そうして自殺を思いとどまったのである。
写真家・藤原新也のエッセイで紹介されているこのエピソードの富士山は、“ただそこにある”だけだった。それでいながら、その神々しい存在によって、彼女の自殺を思いとどまらせたのである。もしこれが富士山ではなく他の山だったらどうだっただろうか。彼女の自殺を思いとどませることができただろうか。
ただ、そこに富士山がある。それだけで、ぼくたちは何かを感じずにいられないのはなぜなんだろう。富士山とは、風景を超えた“なにか”なのかもしれない。
さて、雄大な富士山をテーマにした写真集は世の中にたくさんある。その中でもっとも異彩を放っているのが、ほかでもない藤原新也の異色の富士山写真集というべき「俗界富士」だ。富士山の写真集といえば、美しい自然の風景の中でとらえたものが普通だけど、この写真集はケバケバしい看板越しの富士山だったり、工場や墓地越しの富士山だったりと、いわば“俗界”のなかでとらえた富士山がメインなのである。その序文で藤原新也はこう記している。「私はこれまでヒマラヤやカラコルムといった雪をいただく高い山々を見てきたが・・・それは俗界というものと切り離された”彼方の風景”として眺められる。しかし富士は泥沼と蓮華の花とが一体となってひとつの風景を形作るように、俗界と一体となりながら成り立つ高山なのだ」と。
これこそまさに富士山の本質をとらえた一文ではないだろうか。ぼくたちが普段目にする富士山は、本栖湖の逆さ富士や三保の海越しの富士といった絶景富士山ではない。日常の風景。そう、俗界のなかで、なんの変哲もない町の景色の“へり”に顔をのぞかせている富士山なのである。でも、その俗界にありながらも富士山は、いつでもどこでも超然とした姿でそこにある。コンビニ越しに見える富士であろうが、ビルの間に垣間見える富士であろうが、新幹線の窓から望む富士であろうが、なんであれそれは、あっけらかんと、あくまでも超然としてそこにある。まさしく「泥沼と蓮華の花とが一体となってひとつの風景を形作るように、俗界と一体となりながら成り立つ高山」としてそこにある。
「富士には月見草がよく似合う」といえば太宰治である。太宰の短編「富嶽百景」のなかの有名なこの言葉は、雄大な富士山と小さな月見草の俳諧的な対比というところが一人歩きしているけど、実際は、いかにも太宰らしい、やや屈折した文脈のなかから出てきた言葉だったりする。太宰にとっての富士山は、それが絶景であるほどに「風呂屋の俗なペンキ絵」であり、「芝居の書割みたいな注文通りの風景」であって、そんなものに感動するのは我慢がならないのだった。そんな太宰が河口湖から御坂峠へと向かうバスのなかでひとりの老婆に出会う。バスの車中では乗りあわせた乗客たちが口々に窓からの富士の眺めに感嘆の声をあげていた。ところがその老婆だけは、おそらく地元の人なのだろう、富士には目もくれずに、山沿いの断崖を見つめていた。その様子は太宰にとって「身体がしびれるほど快く感じた」のである。老婆が「おや、月見草」といって目をとめたのが路傍の月見草の花だった。3776mの大きな富士に対峙するかのようにけなげに花を咲かせる月見草。俗にまみれた富士とあいまみえてみじんもゆるがない月見草の姿に太宰は共感をおぼえた。「富士には月見草がよく似合う」という言葉は、月見草に贈った太宰のエールであり、だから「よく似合う」という表現には皮肉が込められている…と、そう解釈したほうがいいだろう。
「富嶽百景」では、太宰が富士山を形容する言葉がコロコロと変わっていく。「小さい、真っ白い三角」「なんのことはない、クリスマスの飾り菓子」「あまりに、おあつらえむきの富士」「風呂屋のペンキ絵」「芝居の書割」「どうにも注文通りの景色」「変哲もない三角の山」「青白く水の精みたいな姿」「のっそり突っ立っている富士山」「山々のうしろから、三分の一ほど顔を出している酸漿(ほおづき)」…などなど。富士の前ではどうにも素直になれない太宰がこうした言葉でケチをつけていくわけだけど、でも、ケチをつければつけるほどに太宰の富士山に対する心のひっかかりのようなものが浮かびあがっていくところが、この小説のツボというべきところだろう。太宰本人だってもちろんそれをわかっている。だからこそ小説にしたのだろう。それはそれとして、「富嶽百景」でもまた、富士山はやはり超然とした姿で、ただそこにあるだけだった。見る者(太宰の意識)への印象を変幻自在に変えていきながら、心を映し出す鏡のようにそこにあったのだ。
そもそも富士山は、たんなる山なのだから「ただそこにある」のは当たり前のことかもしれない。その点においては他の山となにも変わるところはない。でも、冒頭の藤原新也のエッセイのエピソードにあったように、ときとしてそれは自殺を思いとどませてしまうほどの、なにかを秘めているのである。日本一の霊峰と崇められ続けてきた聖なる山はまた「風呂屋のペンキ絵」「芝居の書割」と太宰がいうように俗な山でもあり、そうした絵ハガキ的な俗さにおいても富士山を超える山は他にない。聖も俗も超越して、山であることさえも超越して、ただ超然とした姿でそこにある山。それが富士山なのだろう。