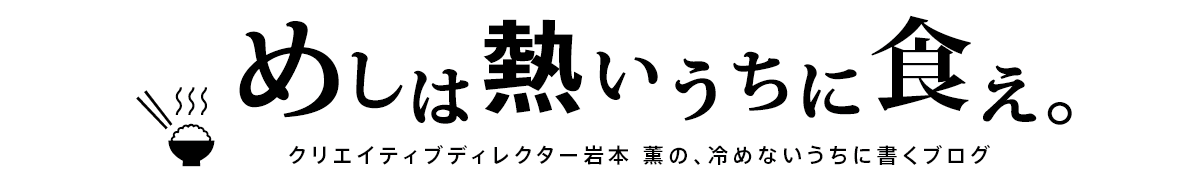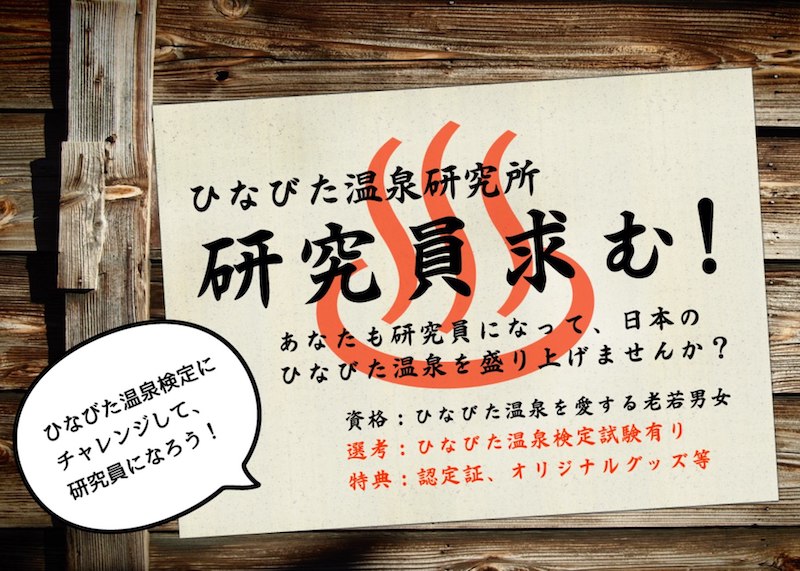古事記は火山の遙かなる記憶なのか?

弟のスサノオのあまりの乱暴狼藉をかばいきれなくなり、腹を立てたアマテラスは、岩戸に引きこもり、そうして世界は闇に包まれた。
古事記に登場する天の岩戸伝説はなにを意味するのか?折口信夫はそれを、冬に衰退する太陽の光の復活を祈る冬至の祭祀に由来すると考えた。いや、そうではなく、あれは日蝕に由来したものだという説もある。……と、ここまでは聞いたことがあるという人も多いと思う。でも、どうなんだろう。冬至の祭祀にしても、日蝕にしても、世界が闇に包まれて、困惑した八百万の神々が岩戸の前に集まって、あの手この手で岩戸を開けようとしたという神話のスケール感とは、なんとなくあわない。いかに冬の太陽が衰退するといっても世界が闇に包まれるイメージとは、ほど遠いし、日蝕だって、太陽が隠れてる時間はわずか数分のことでしかない。そもそも、天の岩戸伝説はアマテラスとスサノオという、いわゆる三貴子の中の2人という古事記の最重要キャストであり、その2人が仲たがいして岩戸騒ぎが起こってスサノオは高天原がら追放されて、そこからヤマタノオロチ退治などのスサノオの冒険譚へとつながっていく。つまり古事記のストーリーの中でもかなりエポックな場面なのだ。そのように古事記の文脈の中で考えると、冬至の祭祀説や日蝕説がいよいよスケール的にそぐわないように思えてくるのだ。
そうではなく、あれは縄文人の火山の記憶なのではないか。最初にそれをいったのが物理学者の寺田寅彦だった。寺田はスサノオを火山のメタファーであると説いた。そして、その寺田のスサノオ火山説をさらに本格的に論として展開したのがロシアからの亡命者だったアレクサンドル・ワノフスキーだった。
かつて……、といっても今から七千年も前のことだけれども、九州の現在でいえば鹿児島の沖合で、すさまじいほどの超巨大噴火があった。現代のシュミレーションによるなら、噴煙は成層圏にまで達して、時速百キロのスピードで火砕流が鹿児島全域はもちろん九州のほぼ半分を火砕流で埋め尽くした。縄文人を含めた九州広範のの動植物が死滅したであろうことが、容易に想像できる。じつはこれ、縄文初期の遺跡や遺物が東北にしかないということと大きく関連している。つまり、この大噴火によって九州の縄文文化は断絶したということだ。
さて、ここでまた天の岩戸伝説へと戻ってみよう。アマテラスが岩度に隠れて世界は闇に包まれた。つまりそれは火山の噴煙によって太陽の光が遮断されたことを伝えているのではないか?破局噴火と呼ばれるこのような超巨大噴火が起こると太陽の光は年単位に渡って遮断される。数分レベルの日蝕とは比較にならない。しかし神話のスケールで物語られる“世界が闇に包まれる”というイメージは、そういうことでなないだろうか。火山のメタファーのスサノオの乱暴狼藉によって、太陽神のアマテラスが岩戸に隠れて世界は闇に包まれる。すなわち、それは、成層圏にまで達した地球レベルの噴煙が太陽の光を遮断したことであると、スサノオ火山説を説くワノフスキーはいうのである。
そもそもスサノオは、父イザナギからおまえは海を治めるようにと命じられたとき、泣きわめいて抵抗した。これもまた、古事記の中で謎に満ちたところである。古事記の記述では、このスサノオの大泣きが山をことごとく枯山にして、海や川の水を干上がらせたという。
どうだろう?荒ぶる神が大泣きしたのならば、普通に考えれば大洪水なのではないだろうか。ところが山を枯れさせ、海の水も川の水も干上がらせたのだというのだ。だからこそ、ワノフスキーはこう解釈する。スサノオが火山神であればその涙は燃えたぎるマグマなのである。それならば山を枯らし水を干上がらせるという、古事記の記述に、なんの矛盾はないのだと。
寺田寅彦やワノフスキーが古事記と火山の関係を説いた、その時代には、この説はあたかもトンデモ説のように、学会ではあまり相手にされなかった。しかし、当時の古事記は国文学や考古学の範疇のものだった。スサノオ火山説なんちゅう門外漢の“思いつき”みたいなものを認めてしまえば、それまで築いてきた“古事記論”がガランガランと音を立てて崩れてしまうのだ、……ということだ。
でも、古事記は、後半こそ天皇たちの物語であっても、前半はれっきとした神話なのである。われわれはどこからきたのか?われわれはなぜこんな世界に生きているのか?われわれとは何者なのか?世界のあらゆる神話と同じように、まだ、書き言葉を持っていない、気の遠くなるような何代にも渡る後世に民が、自分たちの物語を後世に伝えるための古代人共通のフォーマット、それが神話ではなかったか。ことに日本は世界有数の火山大国であり、日本の各地に見られる古い巨石信仰は火山と無関係ではない。それらの巨石はすべて火山の“賜物”なのである。その火山を神として語る神話がなかったことは考えにくい。
すべて紹介するとキリがないけれども、ワノフスキーのスサノオ火山説はもっともっと幅広く奥深い。ぼくがそういう古事記論があるのを知ったのは、蒲池明弘さんの「火山で読み解く古事記の謎」(文春新書)を読んでだった。それがとっても“目からウロコ”だったので、読み終えてすぐさまワノフスキーの「火山と日本の神話」を買って読んだ。
たしかに古事記をこれまでのように、大和民族と先住民との攻防みたいな文脈だけで解釈すると、奥行きが感じられない。とはいえ古事記が編纂された動機を思えば、大和民族と先住民との攻防を正当化するということが重要だったとは思う。でもそんなものだったのだろうか。古事記(とくに前半)はよくギリシャ神話との類似点があげられるように、もっと人類の普遍的なものを物語っているように思えてならないのですね。
縄文時代を襲った(しかも九州の縄文文化を壊滅させたほどの)超巨大噴火は、すでに、当時の世界の中で高度な文明を築いていた縄文時代のことなのである。脳科学的にも縄文人の脳は、ほぼわれわれと同じなのだとされているわけで、後世にまで長きに渡って語り継がれなかったわけがない。そう思いませんか?
いろいろと謎が多い古事記論。でも、そこに“地質学”という壮大なスケール(なんてったって地球の歴史46億年なのだから!)の視点が加わることで、思いもよらなかった新しい発見があるのかもしれない。かつてギリシャ神話のトロイアを発掘したシュリーマンのような大発見が。いや、あるのかもしれないではなく、あってほしい。いやいや、かなりある気がするのですねぇ。
※当サイトのすべての文、画像、データの無断転載を堅くお断りします。