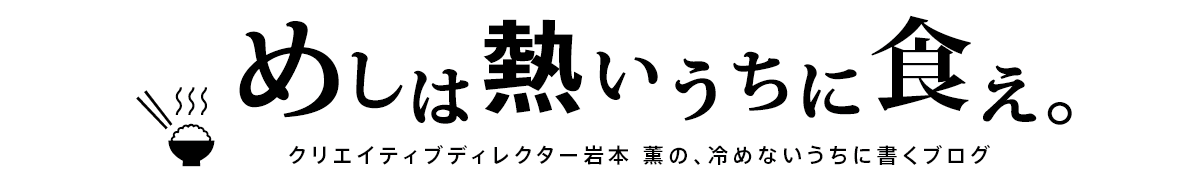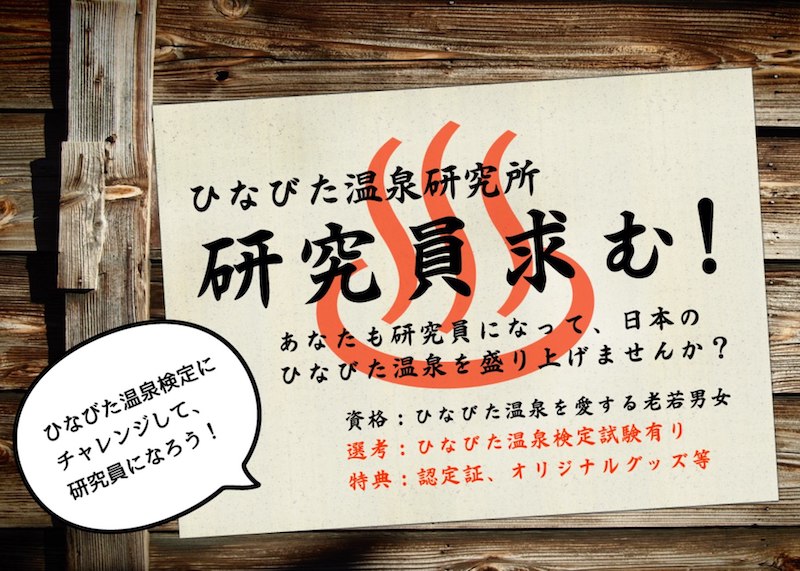セロニアス・モンク、孤高のポツリズム。
「真夏の夜のジャズ」っていうニューポート・ジャズ・フェスティバルの模様を記録したナイスなドキュメンタリー映画があるんですね。ジャズ好きの間では有名なこの映画のどんなところがナイスかっていうと、言葉ではいえないジャズの空気感みたいなものがジワジワと伝わってくるところがすごくいい。参加しているミュージシャンたち、それから観客たち、大人が、子供が、あるいはほろ酔いしたビートニク風の若者なんかが自由気ままにフェスティバルを楽しんでいる様子を、絶妙なカメラワークとコラージュ的な構成で実にいい感じにとらえている。やっぱりこれだよねえ、ジャズは、この自由にリラックスした感じなんだなあ、なんてふうに思わせてくれることうけあいの映画だったりするんです。
その映画の冒頭近くにセロニアス・モンクが登場するんですね。例のごとく、なんか調子っぱずれな感じにオリジナルの「ブルー・モンク」を演奏して、曲が終わると、おずおずとしながらお辞儀をしてステージを降りていく。それ自体は特別に変わったシーンではないんですけど、なんともいえないインパクトと不思議な余韻がある。で、ひいてはこのシーンが、なんだかこの映画の不思議なシークエンスとして、なにげに記憶に残っていたりするわけで、やっぱりモンクは、スクリーンのなかでもモンクなんだなあって、妙な納得をさせられるんですね。なんともいえないインパクトと不思議な余韻。これはそのままモンクのジャズの魅力っていってもいいのかもしれません。
このモンクが登場するシーンで、彼は司会者にこんなふうに紹介されます。
「次に登場するプレイヤーは、非常に独創的な音楽のクリエーターです。彼は自分の音楽を生き、自分の音楽を考え、人生そのものが音楽という人物。彼は尊大なわけではないが、自分の音楽への批判は気にしません。彼が探求しているものは、西洋音楽にはない四分音です。ピアノの隣り合う2つのキーをたたき、その間にある音を“暗示”します。では、セロニアスモンクです。」
いや、これは、モンクの概要をさりげなく網羅していて実にうまいアナウンスっていうべきではないでしょうか。人生そのものが音楽という人物、モンク。ピアノの隣り合う2つのキーをたたいて、その間にある音を“暗示”させるモンク…。おもしろいのは「彼は尊大なわけではないが、自分の音楽への批判は気にしません」っていう、この、もってまわったようないいかたですね。モンクのことを知る人なら、ここはちょっとニヤリとしてしまうところだと思うんですけど、どうでしょう。
「モンクが安定した仕事をえて、ほかのミュージシャンに受け入れられるまでには15年以上の歳月が必要だった」といったのはジャズ・ライターの大御所ナット・ヘントフだったけど、そう、モンクの不遇の時代は実~に長かった。強調しておきたいのは、これ、あくまでも不遇の時代であって、下積み修業時代ではないんですね。というのも、モンクが、ミントンズ・プレイハウスの専属ピアニストとして登場したころ、すでに彼はモンク・ジャズとでもいうべき誰にも真似できない独自のスタイルを確立していた。ハイ、不協和音をダーンッとぶつけてみたり、不思議なアクセントでタイム感覚をガクガクッとずらしてみたりという、あのクセのあるスタイルですね。で、さらにいうならモンクがミントンズに登場したのは40年代はじめの頃。この頃のミントンズはというと、ジャズの大革命というべきビ・バップ発祥の地でもあったわけで、そう、チャーリー・クリスチャンとかケニー・クラークとか、あるいはパーカーとかガレスピーっていう強者たちが、歴史的なジャム・セッションを繰り広げていた頃であった。つまり、専属ピアニストであるモンクも、そうした面々と一緒になって、新人ミュージシャンにとっては脅威というよりほかない革新的なセッションをしていたわけです。モンクの実力については、これはもう、いわずもがななわけですね。
じゃあ、そんなモンクがなぜ長い不遇の時代を過ごさなければならなかったのか?
それは大衆受けしなかったから。つけ加えていうなら、ナット・ヘントフがいうように、ミュージシャンたちにも理解されなかったから。モンクのジャズは仲間内では一目置かれていたものの、あまりに独創的だったため、ミュージシャンたちにとっても受け入れがたいものだったんです。ジャズはお互い挑発しあって、いわば“ノリの感覚”でスリリングな高みにのぼりつめていくような音楽なわけですけど、モンクのジャズはクセがありすぎて、共演者にとっても、どうついていったらいいのかわからない途方にくれてしまうものだったんですね。こうなるともう大衆受けどころじゃない。そんなわけで、モンクのことを積極的に売り出そうというプロデューサーも現れなかったし、また、ぬれぎぬから警察にキャバレーカード(NYでの営業許可書みたいなもの)を6年間も取り上げられるという不運なトラブルもあったりして、モンクは長い不遇の時代を過ごさなければならなかった。
でも、そんなモンクもプロになってから10数年後の50年代後半あたりから、よき理解者にも恵まれ、次々と傑作アルバムを世に送り出して一気にブレイクします。もちろん、それはあくまでも“クセ者”としてブレイクするんですけど(笑)、まあ、よくあるいいかたをするなら、時代がモンクに追いついたっていうことなんでしょうか。
ちなみにジャズ・シーンにおいてのモンクを大まかに3つにわけてみると、1.長い長い不遇の時代、2.ブレイクしてバップの高僧とかいわれて奉られた時代、3.マンネリといわれてしまった晩年、と、こんな感じにわけられます。時代でいえば40年代から70年代まで。思えばジャズという音楽はその間、めまぐるしい変化を遂げてきたわけですけど、なんとも痛快なのは、ジャズのトレンドがどう変わろうと、モンクはほとんどスタイルを変えなかったんですね。誰にも相手にされなくても、いきなり奉られても、マンネリといわれても、このモンクという人はひたすら我が道をいき、そして我が道を極めていった。なんていうか、最初から完成されたオリジナルティーをもってジャズシーンに現れた、ジャズの突然変異体というべき人だった。
さて、というわけでモンクのソロ・ピアノです。フツーではないジャズを極めていったモンクのソロ・ピアノは、そう、もちろんフツーではない。ひと言でいうなら、“ポツリズムの快感”。
ジャズのソロ・ピアノっていうと、バンドから離れたピアニストが華麗なテクニックで、その人ならではの世界を披露してくれますね。ソロ・ピアノを聴く楽しみがそこにあるといっていいかもしれない。たとえば最近では、ビールのCMで小曽根真さんがロマンティックで素敵な「We’re All Alone」を聴かせてくれました。でも、ああいうテイストをモンクに期待してはいけないんですねえ(笑)。確かにモンクも“その人ならではの世界”を披露してくれますけど、「うっとりするような」とか「流れるような」とか「ハッと息をのむような」とか、そういった言葉とは無縁の世界だったりするんですね。ポツリ、ポツリと、なんだかつっかえながら弾いているような朴訥とした独特なタッチでピアノを弾く。なかには「ん?ん?」って思うような演奏もあったりもして、でも、耳をかたむけているうちに、なんだかいつまでも聴いていたくなるような、そんな心地よさがあるのがわかってくる。
そう、モンクのソロ・ピアノには、響きと間を聴く快感がある…。そういってしまいましょう。ポツリ、ポツリとタッチと、不協和音や唐突なシングル・トーン、あるいは不思議なタイム感覚で構築されたモンクのソロ・ピアノの世界は、汲み尽くしがたい響きと間に満ちた世界でもあるんですね。ちょっとヘンな喩えで恐縮なんですけど、たとえばうるめいわしの丸干しとかシバ漬けなんかの味を噛みしめながら白いご飯を食べるてると、粗食の快楽っていうか、じわじわ~っと幸せがこみ上げてきますよね。それに似た喜びがあるのがモンクのソロピアノなんです。ビル・エヴァンスやキース・ジャレットのピアノが極上グルメの味わいならば、モンクのピアノはそうしたグルメからは味わえない“ココロのふるさと系”の味がある。あるいは滋味というべきか。
ジャズ・ドラマーでもあるモンクの息子、モンクJrは、父モンクがピアノを練習していた様子をこんなふうに回想しています。
「その当時の父は1日1曲のペースでひどく集中した練習をくり返していた。朝の7時くらいからはじめて、午後の3時くらいまで、その曲のメロディを何度も噛みしめるみたいに弾いていたのをよく覚えている。父はその練習についてなにも語らなかったし、僕もまだ若かったから、その練習からなにが得られるのかわからなかったんだ…」と。
ひどく集中して、その曲のメロディを噛みしめるように何度も何度も弾いていたモンク。こうした練習方法でなにを目指していたのかは、本人じゃなければわからないことですけど、その結晶が“ポツリズム・ピアノ”であることは確かといっていいんじゃないでしょうか。そういえばどこかでモンクのピアノは禅に通じるなんてことを読んだことがあります。なんだかよくわからないけど、わかるような気がしないでもないですね。ポツリ、ポツリと弾かれるモンクのソロ・ピアノの美しさは、決してダイレクトに表に出てはこない。わかりやすいか、わかりにくいかっていうと、あきらかにわかりにくいかもしれないけど、でも、そういうのって、ちょっとボーッとしながら耳をかたむけていると感じられたりもするわけで、ハイ、そんなわけでモンクのピアノはボーッとしながら聴くのがベストなのかもしれません(!?)。
さて、モンクのソロアルバムはというと、どれも甲乙つけがたい、味のあるアルバムなんですけど、ここでは先にふれたようなモンクのソロピアノの滋味がよく現れている2枚をセレクトしてみました。
ポツリ、ポツリがじわじわ心にしみる、
これぞモンクの孤高の美学
「セロニアス・ヒム・セルフ」
そう、モンクの“ポツリズム”はこのディスクでどっぷりと堪能できます。モンクの名曲「ラウンド・ミッドナイト」がモンク自身のピアノで聴ける…。それだけで聴く価値があるっていってしまいましょう。ところがこのCDにはさらにボーナストラックとして「ラウンド・ミッドナイト」のボツ・テイクというか、モンク自身が納得いくまで粘り強くソロ・ヴァージョンを完成させていく過程をおさめたトラック(約22分!)が加えられています。これが聴いていてとても興味深い。スタートミスがあったり、途中放棄があったり、モンクの集中力が聴いている側にも伝わってくるスリリングな内容です。
アルバムは1曲以外すべてがモンクのソロピアノ(あ、その1曲もコルトレーンがサックスで参加しているスペシャルな内容です)。一音、一音を噛みしめるように弾くモンクの内省的な滋味あふれるプレイ…。夜のしじまの中で、ひとり放心状態で聴くのがおすすめのシチュエーションです。ソロピアノを愛するすべての人のための“夜の愛聴盤”(なんだか“うなぎパイ”みたいですけど)として、だんぜんおすすめの1枚。
モンクのポツリズムファン必聴
「あなたの眼がこわいの」がおさめられた1枚
「アローン・イン・サンフランシスコ」
いつになくニコニコしたモンクが、サンフランシスコ名物のケーブルカーに乗っているというお茶目なジャケットのこのアルバムは、プロデューサーのオリン・キープニュースが偶然、サンフランシスコでモンクと会ってサクサクサクっと行われたレコーディングの賜物だった。というわけで、急な話しだったことからスタジオがとれず、代わりにとあるホールでレコーディングされたのだと…、そんないきさつがあったらしいんですね。で、結果的にそれが幸いしたようなんです。スタジオと違って厳密な時間制限のないレコーディングは、リラックスして行われて、モンク本来の持ち味をうまく引き出した吹き込みとなった。
そんなリラックス・ムードがこのCDからじわじわと伝わってくるわけです。だから聴いているほうも、なんだかいい~感じになってくる。注目したいのが「あなたの眼がこわいの」という曲。(こういうタイトルの曲を、ほかならぬモンクがひいているっていうのも、ちょっとおかしかったりするんですけど)モンク自身が古いソングブックの中から見つけたという、この聞き慣れないスタンダードは、あんまり話題になることもないけど、とても素晴らしいんです。訥々としたモンクのピアノの魅力がにじみ出た貴重な録音ですね。これこそモンク・オンリーな味。いつまでもいつまでも聴いていたくなるような、なんともいえない魅力がありますから。